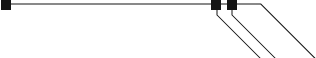日中の島は音に満ちている。鈍く空気を揺らす波はしかし、かつてこの一帯を満たしていた、騒々しくも心をかき立てる調べではなかった。建材を運ぶ車両の駆動、地面をうがつ重機の振動。私は耳をふさぐ代わりにフードをかぶる。防音にさして効果はなく、雨粒が布を打つ音が加わっただけだった。
小高い丘に位置する旧γ(ガンマ)地区からは、小さな<島>の様子が一望できる。以前は夜になれば闇に包まれていたこの島も、今はその半分が昼夜問わずほのかな光に包まれている。島をじわじわと侵食する<ケルビム>の光を観察するに、“復興”は東側から進んでいるようだった。最西端に位置する旧γ地区に<AO>の手が入るのはまだ先のようだ、と私は見当をつけるが、その希望的観測に大した意味はなかった。根城にしているここ一帯にもいずれ、<ビーイング>を着けたAOのオペレータがやって来る。丘がすべてケルビムに覆われ、旧γ地区が光に包まれたとき、島の復興は完遂されるだろう。私は丘を下りながら淡々と考える。
麓には、AOによって整備された居住区が広がる。フードを目深にかぶり直したが、雑踏を形成する人々は誰も私に目を留めない。夜の散策は最近頻度を増していたが、別段目的があるわけではなかった。当初は今後を見据えた食糧調達のためだったが、道には食べ物どころかごみひとつ見当たらない。そもそも、旧γ地区にはわずかながら食糧や住居が残されている。つまり麓エリアの散策は、AOに拘束される危険こそあれ、得られるものは何もない。それなのに、私の足は毎夜街に向かう。強いて言えば、自由の誇示かもしれない、と左手が首をなぜたとき、私は不意に立ち止まった。
「自由?」
つぶやきとともに、低い笑いが込み上げてくる。人々の群れはせき止められることなく、私を避け緩やかに流れていった。
自由。私がかつてこの島で手にしたと思っていた“それ”は所詮、かりそめのものではなかったか。もう忘れたのか、ノア。漏れ出る笑いは自嘲にほかならなかった。この世界で一番自由を謳歌(おうか)していたはずの私。それがどうだ。今やなぜ歌っていたのか、それすらわからない。マリオネットの瞳に糸が映ることは決してないのだ、と私は左手を掲げる。──今この手に糸がついていないと、なぜ言い切れるだろうか。視界の端でケルビムが明滅している。私は再び歩き出す。そう、今の私は、自由。なんて自由なの。自由だから、漂泊するほか何もできない。私はただ、行き交う人たちを眺める。左手にビーイングを着けた彼らのほうが、私よりずっと自由に見えるのが不思議だ。
復興が完了したエリアは、かつて暮らしていたAOをいやでも想起させる。この街のどこかに、かつての仲間がいる。花譜はどうしている。カリオペは。彼女たちと同じく、<UMD>で来たとかいうあの子は──そしてシュカは。皆ビーイングを着けて、このエリアのどこかで暮らしているのだろうか。目の前にオペレータの一団を見つけ、私は反射的に薄暗い路地裏へと隠れた。
息をついた私の足元で、何かがうごめく。一瞬身構えたが、それはケルビムの光を反射した水たまりだった。通りから差し込むケルビムの光が水面に映り、色を変えていく。私はつま先で水たまりをつついた。水と同時に光はゆらぎ、すぐさま元に戻る。何度か繰り返した後、無性に腹が立って水面を踏みつけた。しずくが光を反射しながら飛び散り、つま先が湿っていく不快感だけが残された。オペレータが通り過ぎたのを確認した私は、わずかな徒労感と共に路地裏から出る。帰ろう、と見上げた旧γ地区だけが、取り残されたように暗くたたずんでいた。
あの日島にリオが来てから、20日がたとうとしていた。島の変貌には驚くべきものがあったが、何より解せないのは、それが加速度的に速まっていくことだ。このペースだと、数日のうちに旧γ地区までAOの手が伸びるかもしれない、と私は人の波に逆らいながら先刻の考えを改める。しかしそれも、今の私にはどうでもよいことだった。
島にリオが来た日から私は、歌うことができなくなっていた。
*
リオがやって来た日から、島からは歌が消えた。私以外、消えたということにすら気がつかないうちに。
しかし、歌のない島で私が驚いたのは、世界のにぎやかさだった。
旧γ地区への道を重い足取りで上る。その足元を、小さな光が彩った。顔を上げると、視界いっぱいに広がるチドリの群れ。小ぶりな翼が月明かりを乱反射し、地面に光のかけらを散らした。薄片は一瞬でほどけ、次の列の羽ばたきへ受け渡される。
「世界は、こんなにも歌に満ちていたんだ」
鳥の鳴き声も川のせせらぎも、もちろんケルビムを設置する重機の軋(きし)みも、“音”ではあるが“歌”じゃない。しかし、縦横無尽に空を行く旅鳥は──音こそしないものの、まさしく歌だった。聞こえないはずの旋律に耳を傾けると、少しだけ満たされた思いがする。上空の鳥たちに寄り添うように、私は唇を開いた。
重力の平面を脱したチドリの群れには、高低の軸が存在する。加えて、三次元上に構成される隊列が密集・散開するとき、そこには速度により抽象化された時間が見てとれた。また観察を続けるうちに、群れの発生する頃合や飛行の軌跡にはっきりとした規則性──つまりは反復──があることにも気がついたのだ。
起伏と時間、そして反復。
チドリの配置が音程の高低、速度変化はリズム、そして規則性がモチーフとするならば。私の頭上で展開されているのは、構造としての“歌”にほかならなかった。群れをなす一羽一羽は五線譜の空を行く旋律の粒子。音こそ持たないが、飛翔する彼らは歌そのもの。聞こえないメロディに合わせて唇を動かしてみる。私の喉が空気を震わせることはなかったが、今はそれでも構わなかった。自由に飛ぶ鳥たちと私は、沈黙の調べを介して同じ鼓動の未来を共有しているのだから。
「そんなことに、いまさら気づくなんて」
聞こえない歌を奏でるのはチドリの群れだけではない。にわかに軽くなった足取りで、私は丘を一気に駆け上る。旧γ地区の頂上からは、島を彩るさまざまな歌が感じ取れた。周囲を流れる川も、風に揺れる木々も、絶えず何かを奏でている。月も、星も、雨だってそう。それに──
私の視線は丘の下へ向いた。ささやかな月明かりを塗りつぶすケルビムの光。そのきらめきに縁取られた島と、行き交う人々。ケルビムの映す具体的な情報までは読み取れなかったが、自在に色を変える幻想的な光景はいくらでも眺めていられた。単基でも目を惹(ひ)く美しさだったが、広がるケルビム群全体を俯瞰(ふかん)すると、島全体が巨大な生き物のようだった。仔細に見れば、すべてのケルビムは異なるリズムでその光を変え、それらが織りなす周期的なうねりが島を蠕動(ぜんどう)させているのだ、と理解できた。
私は長いため息をついた。ケルビムはビーイングと並ぶ、AOの先進性と支配の象徴。そう信じていてもなお、光に包まれていく島は美しい。
「そして……これもまた、歌なのね」
認めざるをえなかった。緩やかに形を変えるケルビムの光、その下で暮らす市民たち。緻密な計算の結果造られた人工物には違いなかったが、ケルビムに照らされた島もまた無音の歌を奏でている、と私は思う。島の呼吸に合わせ、拍を刻むかのように体が揺れた。今しがた根城までたどり着いたというのに、またあの光の下に行きたくなる。胸の中心がわずかに疼(うず)いた。
そもそも、と私は自問する。なぜ私は、リオがAO市民を操っているだなんて考えていたのだろう。眼下の光景は、統治や強制といった言葉とは程遠いものだ。温かくて、滑らかで、そして自由。旅鳥の群れや川の流れが何ものにも縛られていないように。
私は何か、重大な思い違いをしていたのかもしれない──
思考を遮ったのは耳障りな鳴き声だった。見上げると、チドリの群れはすでになく、集団からはぐれた一羽が頼りなく飛んでいるのみだった。迷鳥(まよいどり)か、と一瞥(いちべつ)した私は、再び麓の光に目をやった。
(温かくて、滑らかで、そして──誰ひとり、操られてなんかいない。だって、こんなにも皆、自由に生きているんだもの)
鋭い鳴き声が断続して響き、うんざりした私は再び顔を上げた。夜空に描かれる不恰好な軌跡。かつて島にもあんな子がいた──そう思ったとき、チドリの翼が月光をはじいた。光の薄片が目を刺し、反射的にまぶたを閉じる。一瞬の暗闇に残った光の残滓(ざんし)が、私の記憶の奥底を照らした。
「温かくて、滑らかで……なのに、どうして……?」
かつてこの島は、有り余る自由の象徴だった、と私はゆっくりと目を開ける。今目の前に広がる光景、そこで生きる人々もまた、自由には違いなかった。しかし、安寧に満ちた街は以前の島とは正反対だ。
混乱しかけた私の口から「あっ」と声がこぼれる。
ケルビムの光に照らされた島は、あまりにも凪(な)いでいた。穏やかで、温かく、滑らかすぎた。まるで「自由」の甘い箇所だけを巧妙に切り取ったかのような……しかし、その思いつきは抽象的でつかみどころがなかった。私は千々に乱れる思考を必死につなぎ留める。
言いようのない違和に実体を与えたのは、島が奏でる沈黙の旋律──それに合わせて揺れる自分の体だった。
(この波は……ホケトゥス?)
ひとつのメロディを意図的に分断し、細切(こまぎ)れになった旋律を複数の演者に割り当てる技法──ホケトゥス。異なる演者が演奏と休止を交互に担い、細断された旋律をひとつなぎのメロディとして再構築する、古典的な音楽理論だ。単なる役割分担ではなく、理想とする構成から逆算され割り振られた順序と沈黙。それらが奏でるのは、個では決して生み出すことのできない、調和の妙。ホケトゥスは、構造そのものに意味がある。
ケルビムが奏でる歌は、一見チドリたちのそれとよく似ていた。しかし、旅鳥の群れは一羽一羽の自由な羽ばたきの集積。片やケルビムの光は、群体の奏でるべき旋律を分解し、個体ごとに割り振ったもの。異様なまでの滑らかさは、総体としてのメロディがあらかじめ決定されていることの証左だ。
そして、同じ拍動を刻んでいるのは、光だけではなかった。
「ケルビムだけじゃない。人も、モビリティも……島全体が、ホケトゥスを奏でている」
私は何か、重大な思い違いをしていた──先刻の投げやりな考えは、ある意味では正解だったのかもしれない。私は逸(はや)る心をなだめるように思考を深めていく。
ホケトゥスを奏でるケルビム群。それにシンクロする人々。島全体が発する、よどみのない、清らかな──清らかすぎる旋律。私は目を見開いた。
「それぞれが違う役割、異なる行動をとるように導かれているというの……?」
なんのために? AOが、リオが目指す調和のためだ。光の下で暮らす人々の営みは、AOの目指す理想から遡(さかのぼ)ってデザインされたもの。あらかじめ完成された旋律があるから、互いが衝突することもありえない。
あまりにも荒唐無稽な考えに思え、私は頭を強く振った。しかし、だとすれば麓の居住区で気がつかなかったのも納得できる。ホケトゥスの構造は全体を俯瞰しなければ理解できない。この島でそれが可能なのは、旧γ地区にいる私だけなのだ。
「みんなを操っているのはビーイングじゃない。ケルビムだ。ケルビムの、あの光だったんだ」
つぶやいた私の脳裏で、あの日のリオの言葉がこだまする。
「ケルビムには、もっと有効な使い方があるんだよ……」
ケルビムの、本当の使い方。それが、これなのだ。心臓が大きく跳ね、私は右手で胸を押さえた。さっきだって、AOの象徴として忌み嫌っていたはずのケルビムを恍惚(こうこつ)と眺めていたじゃないか。どうして気がつかなかったんだろう、と私は急に襲ってきた寒気に歯を食い縛る。
何より、私は自らビーイングを壊せた。それが、私がずっと自由だったことの、何よりの証左だ。悔恨のあとに押し寄せてきたのは怒りだった。どうして信じられなかったんだ。みんなが信じてくれた、自由だった私のことを。
私は駆け出していた。温かな光に満ちる、眼下の居住区を目指して。
*
光と人に満ちる居住区に戻ってきた私は、荒く息を吐きながらあたりを見回す。建造物に、路面に、視界のあらゆる所に設置されたケルビム。この島が真にAOの支配下となるとき、それは島がすべてケルビムに覆われたときだ。私は雑踏の中、固く目を閉じる。そうしてもなお、まぶたを照らすケルビムの光が皮膚から染み入るようだった。私は誰にも操られてなんていない。もう一度、みんなを自由にできるのは私だけ。意を決して目を開き、顔を覆っていたフードを払った。勢いを増した雨が額を打つ。
「みんな聞いて!」
目いっぱい息を吸い込んで叫んだ。
「みんなを操ってるのは、ビーイングじゃない。ケルビムの光なの」
四方のケルビムを指しながら訴える。が、嗄(しゃが)れた声に、振り向く者はなかった。私は構わず叫び続ける。
「あの光を見てはだめ……」
雑踏の中、声を張り上げ続けても、足を止める者も、こちらに視線をやる者すらいない。
「AOは、ケルビムであなたたちを動かしているんだから!」
まるで、私の姿が見えなくなったかのようだった。
「どうして……?」
嗚咽(嗚咽)交じりのつぶやきも、雨と人々の足音にかき消された。どうして、誰も振り向いてくれないんだろう。ケルビムが私の声を塗りつぶしているから? かつての島で、私が誰の言葉にも耳を傾けなかったから?
「歌なら、届いたのかな」

かつて私の歌は、AOのみんなを自由にした。それなのに、今はどうだ。私の言葉に、誰ひとりとして振り向いてはくれない。歌じゃないと、届かないの? 私は濡れた地面に膝を突いた。
やっぱり、歌を失った私にはなんの力もない。ううん、本当は最初から、なんの力も持っていなかったのかもしれない。私は誰のためにでもなく、ただ、自由に歌っていただけ。歌以外何もできないから、歌えなくなったんじゃないか。みんな、いなくなったんじゃないか。
濡れた地面がケルビムの光を映す。なぜ、私の歌はみんなの魂を自由にできたんだろう。どうして、みんな私の歌を求めてくれたんだろう。 何をするために、私はここへ戻ってきたんだっけ……。
*
「この島に、AOの人たちが来たときのことを覚えてる……」
雨音の向こうに声が聞こえた。顔を上げると雨が目に入り、視界が滲(にじ)んだ。ぼやけた人影は抑揚のない声で続ける。
「あたしが、あの人たちを島に呼んだの」
なぜ、と言いたかったが、嗄れた喉からは空気の音しかしなかった。目の前の少女──遠くを見つめるシュカの瞳は、ケルビムの光を映していた。
「ノアが、歌わなくていいように。あなたから歌を取り上げようと思ったの」
私は肩で息をしながら立ち上がった。ケルビムの光を遮るように、彼女の前に立つ。
「シュカ」
ようやっと絞り出した声は、果たしてシュカに届いたのか。彼女は澱(よど)みなく続ける。
「みんなの声に応えなくていい。歌わなくていい。ノアは、生きててくれたらそれでいいんだって……でも」
シュカが初めてこちらを見据えた。
「ノアにとって、歌は、生きることそのものなんだよね」
そうじゃない。私はシュカの両肩をつかんだ。だって私は、この島で生きているもの。さっきみたいに、大声でそう言いたかった。でも。もしも、シュカにまで伝わらなかったら。私たちを横目に通り過ぎる人たちみたいに、シュカにまで私の声が届かなかったら。恐怖は喉の奥で膨らみ、息をするのも苦しくなった。
「あたしがノアから歌を取り上げたのは、間違いだった」
違う。あなたは間違っていない。そう言いたくて、肩をつかむ指に力をこめる。シュカの顔がゆがんだ。
「この街では、歌い方もわからないの。あたしが選んだのは間違いだったんだよ……」
「違う!」
私はほとんど叫んでいた。ちらとこちらを見る人もいたが、皆何事もなかったようにその場を後にする。シュカだけが、私を見ていた。
「違う、違うよ、シュカ。あなたは、自分で選んだんでしょう」
両手をシュカの頬にそえる。雨に打たれた冷たい肌。
「あなたの選択が苦しみを伴ったとしても、それは間違いじゃない。間違いなわけがない」
「でも、あたしのせいでノアは……」
「あなたが自分の意思で選んだ。それだけでいいんだよ、シュカ」
手のひらに感じるほのかな熱。それがシュカのものか、私のものかはわからなかった。気がつくと恐怖は消えていた。
「それに、あなたは私を見つけてくれた。歌を失ったこの街で」
私はシュカを抱き締めた。一瞬シュカは体を硬くしたが、それでもされるがままになっていた。想像よりずっと小さく、か細い背中。
「大丈夫、シュカ。今度は、私が選ぶ」
*
水面が大きく隆起し、船体が激しく揺れた。急激な圧力の変化で、あちらこちらの壁が軋む。舟は川底の泥を撒(ま)き散らしながら、力強く上空へと浮上する。どこからか飛んできた細かな部品が足元に転がった。重要なパーツでなければいいのだけれど。
「最後のフライトかもしれないね、シュカ」
「ノア……縁起でもないこと言わないでよ」
あの日、リオやオペレータを島に呼んだシュカは、彼らが来る直前、積められるだけの荷物を積み、舟を川底に隠していたのだという。
「とにかく、もう一度歌を取り戻さないと」
決意を込めてつぶやく私に、シュカが心配そうに尋ねる。
「方法は、あるの?」
「大丈夫」
「ねえノア。また歌えるようになったら……」
「大丈夫だって!」
不安そうなシュカの問いに、自らを鼓舞するように断言する。
「そのために、シュカに舟を動かしてもらったんでしょう? 心配しないで」
舟は光学迷彩機能によりその身を隠してはいるが、こんなものでAOの目があざむけないことはあの日リオから宣告されている。それより、と私は唇を噛んだ。この舟もUMDと同じく、元はといえばAOで運用されていたもの。空に溶け込む機体表面の光学迷彩も、ケルビムの類に違いなかった。自分たちを操っていた道具と知らず嬉々として使っていたと思うと無性に腹が立つ。
「ずっと見ていたよ。君たちの島が、どうなるのかを」
リオの言葉がよみがえる。今も、リオの思いどおりだとしたら? 私がこれからすることさえ、リオの手のひらの上での行動だとしたら。私は大きく息を吸って、不吉な予感を振り払った。
「シュカ、光学迷彩を無効化してくれる……」
「え? でも、それじゃ地上から舟が丸見えだよ」
「いいから、早く切って」
シュカは何か言いたげだったが、大人しく舟のコンソールに手を滑らせた。
大丈夫だ。今までの私も、今の私も、誰にも操られてなんかいない。私が選び取った結果が、私なんだ。だとしたら、今すべきことはひとつ。