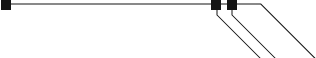舟は島のはるか上空を旋回している。窓に目をやると、眼下には厚い暗雲が広がっていた。地上の目からはしばし逃れられそうだが、そんなものは気休めに過ぎない。彼らにとって、私たちの居場所をつかむなど造作もないこと。だから、急がなくては。
鈍い振動を全身に感じながら、まぶたを閉じ、息を吸い込んでみる。かつて幾度となく繰り返し、体に染み込んだはずの旋律をなぞるべく口を開いたが、やはり空気は喉を震わせることなく抜けていった。
(でも、いい)
目を開き、むき出しの喉に触れる。首筋のひやりとした感触とは裏腹に、久しぶりに感じる高揚で体の奥が熱を帯びていた。船体中央に鎮座するUMDのタラップに足をかける。一段ずつ上がるたび、その熱は増していく。島をひとりさまよっていた頃の絶望はとうに消えていた。
シュカが舟にUMDを積み込んでくれていたのは僥倖(ぎょうこう)だと、私はコンソールにそっと触れた。これを使えば、もう一度、花譜やカリオペを呼べる。
「UMDってどうやって動かすんだっけ」
舟の操縦席に座るシュカに声をかける。もちろん、花譜たちが来てくれたとて、私が歌を取り戻せる保証などない。それでも、論理を超えたところにひとかけらの確信があった。かつて私の歌が、人々を自由にしたように。シュカが、私をもう一度立ち上がらせてくれたように。花譜とカリオペが、私の何かを解き放ってくれる、きっと。
「ねえ、シュカってば」
再び呼びかけた直後、舟の振動が小さくなった。シュカが船体をオートパイロットに切り替えたのだ、とわかったが、彼女は相変わらず窓の外を見つめているようだった。
「……シュカ?」
「また、歌うの」
シュカは振り返ることなく口にした。「みんなを自由にするために?」
彼女は何を言っているのだろう。まだ、ケルビムの影響が残っているのかもしれない。怪訝(けげん)な視線を背中で感じたのか、小さな肩がわずかに震えた。
「これじゃあ、今までのノアと同じだよ」
意図は読めなかったが、シュカの言葉には確かに彼女の意思があった。ますます訳がわからない。かつて自由に歌っていた自分自身を取り戻す。それ以外の目的などない。シュカもそれを願ってくれたではないか。だから、AOから舟やUMDを守ってくれたんじゃないの。今だって、そのために力を貸してくれてるんじゃないの? そう言いたいのを辛(かろ)うじてこらえ、シュカの言葉を待つ。
「ノアの歌はすごいよ。みんなをまた、AOから、ケルビムの支配から解き放つことができる。きっと」
「そうだよ」
私は努めて落ち着いて言った。
「だから、私はもう一度歌う。その何が気に入らないのよ」
「その後はどうするの? 同じことを、繰り返すの」
振り返ったシュカの目はわずかに濡れていた。頭の奥がかっと熱を帯びる。熱源は、先ほどまでの高揚感ではなかった。
「どうしたの、シュカ。ケルビムで操られてた生活が、そんなに心地よかった?」
シュカが力なく首を横に振る。違う、私はそんなことが言いたいのではない。それなのに。
「シュカだって選んだんでしょ。今度は私が選ぶの。ううん、私はこれまでもずっと、自分ひとりで選んできた。あんたたちが島で享受してきた自由を、私は自分の手で選んできたんだよ。私は、元の私に戻りたいの!」
シュカは私を助けてくれた。舟もUMDも、彼女の機転がなければ今頃はAOのオペレータたちの手に落ちていた。そう頭ではわかっていたが、ほとばしる言葉を止めることができなかった。
「私が歌った後、どうするかって? そんなことどうだっていい」
「どうでもよくないよ、ノア」
席を立ったシュカは、こちらに歩みを進めながら断言する。UMDへ続く階段を上った彼女は、私の目を見て続けた。
「島での生活は楽しかった。でも、みんなバラバラになった。ノアも歌えなくなっちゃった。あたしは、あんなノアを見たくない。同じことを繰り返してほしくないの」
シュカの目は、もう濡れていなかった。反論の意を込めて視線をぶつけても、彼女は目をそらすことなく続ける。
「あたしは、ノアにもう一度歌ってほしい。ノアもそう望むんだったら、なんだってする」
「じゃあ、今すぐUMDで花譜たちを呼んで。そして舟を島の真ん中に下ろしてよ」
「ノアがどんな選択をしても、あたしはそばにいるよ。だけど……」
「だから力を貸してって言ってるじゃない!」
思わず伸ばした手が、シュカの肩を突く格好になった。不安定な船内で、シュカの体が傾く。あっ、と思った直後、よろめいた彼女は背後のコンソールにぶつかり、UMDのタラップから転げ落ちた。
「シュカ!」
思わず駆け寄ったが、シュカはUMDのコンソールに打ちつけた腕をさすって顔をしかめただけだった。けがはなさそうだ、と安堵(あんど)したとき、舟とは別の振動を足裏に感じた。振り返ると、背後のUMDが青い光を放っている。
「ノア、あれ……」
シュカも UMDを指差し言う。コンソールに与えた衝撃で、UMDに誤作動が起きたのだろうか。 UMDから伸びる光の筋は次々に増え、船内が青く染まる。思わず眼前に手をかざしたとき、鋭い金属音がした。直後、UMDの中心からひときわ輝く一条(ひとすじ)の閃光が立ち上り、目の前が真白に満ちた。シュカが短い悲鳴と共に、私の手を強く握った。
何が起きている、と白一面の視界のなか必死に思考を巡らせる。目の前では、おぼろげながら人影が動いているのがわかる。影はゆっくりと立ち上がり、頭を押さえるしぐさをしている。
「頭がぐらぐらする……」
聞き覚えのある、か細い声。視力が徐々に戻ってきた目に映ったのは、きょとんとした顔の花譜だった。船内の光は消えていた。
「花譜ちゃん!」
シュカが駆け寄り、花譜に抱き着く。何が起こったのかわからない様子の花譜は目をしばたたかせながら、座り込む私を見て驚いた声を上げた。
「シュカちゃん……ノア!?」
「花譜ちゃん! 会いたかったよう」
「ここは……舟ね。私、また戻ってきたんだ」
花譜は周囲を見回しながら、シュカの背中を優しくなでる。何があったの。島のみんなは大丈夫なの? 花譜の問いかけに、シュカが涙ぐみながら答える。泣きやんだかと思えばまた泣いて、忙しい。シュカに謝る機を逸した私は、行き場のない感情を抱えたまま窓の外を見ていた。
背後では、シュカの説明に花譜が時折驚きの声を上げている。みんなを操っていたのはビーイングではなく、ケルビムと呼ばれる情報投影膜だったこと。島が再びケルビムに覆われたとき、AOから完全に歌が失われてしまうということ。シュカの言葉に、花譜がうーん、と考え込んだ。
「それでね。花譜ちゃんやカリオペちゃんがもう一度来てくれたら、また歌えるようになるかもしれない、ってノアが言うんだけど……」
「シュカ、それ以上はいい」
慌てて割って入ったが、シュカは構わず花譜に問いかけた。
「花譜ちゃんは、歌えなくなったことはないの?」
「シュカってば! よけいなこと言わなくていいんだよ」
一喝すると、シュカが不満そうに口をつぐんだ。花譜は心配そうな顔で私とシュカを交互に見比べている。本当に自分が嫌になる、と私は大きなため息をついて膝を抱える。いったい何がしたいんだ、私は。花譜やカリオペをもう一度呼び出そうとしたのはほかならぬ自分なのに。シュカに指摘されたように、自分の歌が再び混沌(こんとん)を招くことを恐れているのだろうか。いつもの癖で首に手が伸び、そこにチョーカーがないことにまたいら立つ。
「よくわからないけど……シュカちゃん、ノア、とにかく聞いて」
顔を上げると、花譜が目の前に立っていた。相変わらず表情には困惑の色が見てとれたが、やがて意を決したように小さくうなずくと、静かに言った。
「私の歌を歌うね……」
花譜の唇が開くと同時に、船内の空気が一変した。彼女が島で何度か歌ってくれた曲。私は目を閉じ聞き入る。全身が何かに包み込まれるような温かさ。それでいて予想を裏切り駆け回る旋律は、聞く者の油断を許さない、心地よい緊張を含んでいる。やはり、この声だ。私は間違っていなかった。こんなにも、心に響く。
それなのに……それなのに、なぜだろう。もたげた疑問が私の目を開かせた。私の中の歌は、いまだ眠ったままだ。疑念が伝わったのか、花譜は歌うのをやめた。彼女はほう、と息をつくと傍らにしゃがみ込み、左手で私の手を握った。そして目を閉じると、右手を自分の胸に当て、再び歌い始めた。
それは、初めて耳にする歌——の、ようだった。断言できないのは、確かに聞いたことのないメロディなのに、私の記憶の真芯を揺さぶる何かがあったからだ。
(いや、違う……)
喚起されたのは郷愁の類ではない、と心の中で首を振る。花譜の口からあふれ出る音も、刻まれる律動も、ノスタルジーとは程遠い激しさがあった。激情は次第に天を衝(つ)く火柱となり、その周囲を火片の螺旋が舞い躍る。つないだ花譜の手から伝わってくる鼓動が、私の心臓と響き合う。激しく、自由で、初めて聞くはずのこの歌のことを、私は知っている。誰よりも、今歌っている花譜よりもずっと知っている。今にも声を重ねられそうなほど。これは、なんなのだ。今まで秘められていた、花譜の持つ力なのか。私は大きなうねりに身を委ねたまま、歌う彼女をただ見つめていた。
花譜がゆっくりと目を開き、私は歌がやんでいたことに気づいた。どれぐらい時間がたっただろうか。それは数時間にも、一瞬だったようにも思えた。
「私の世界は、ノアやシュカちゃんたちの世界と少し違っていてね」
伏目がちに話し始めた花譜に、歌っていたときの堂々たる貫禄はなかった。ささやくような彼女の声を逃すまいと、私は彼女の言葉に耳を傾ける。
「どれだけ歌っても、どんな人が聞いてるのか、そもそも聞いてくれてる人がいるのかさえ、よくわからないんだ」
ふうん、と返事が曖昧になったのは、彼女の意図を測りかねたからではない。
「花譜の言いたいことはなんとなくわかる……気がする。でも、誰が聞いてたって、たとえ誰も聞いてなくたって、そんなの関係ないと思うけど」
そうつぶやくと、花譜はほほ笑んで続ける。
「ノアは自由で、強いよ。だからみんなあなたに憧れたんだもん。でも、私は違う」
「わかる。あたしもそう!」
無邪気なシュカの言葉に、そうだよね、と花譜がうなずく。
「ねえシュカちゃん、さっき『歌えなくなったことはないの』って聞いたでしょう?」
「うん」
「私の歌が、誰に聞かれてるのかわからなかった頃。誰にも届かないのなら、私の歌に意味なんてあるのかな?って、ずっと不安だった。歌うことが怖かったときも、歌うのなんてやめちゃおうと思ったときもあった。でもね」
つないだままの花譜の手に、わずかに力が込められた。
「あるとき、私の歌を聞いた、って人に会ったんだ。たったひとりだけどね。でも、この世界に私の歌を聞いてくれてる人がいる、私の声が届いてる人がいるんだ、ってはっきりわかったの。そのことを知ってから、怖くなくなったんだ」
「どうして」
尋ねる私の声はかすれていた。
「私の歌が誰かに届くなら、そこに意味があるって思えたから。そして——」
花譜が胸に当てた手を握った。
「その人のために歌おうって思えたから」
花譜の真っすぐな言葉が、頭の中の靄(もや)を払っていく。誰かに、届く歌。誰かに届けるための歌。ならば、さっきの歌は。そう口にする前に、そうだよ、と花譜がうなずく。
「今の歌はね、あなたのことを思って歌ったの。ノアのため——ノアだけのために」
「私のための、歌」
「ノア、今は歌えないって聞いたけど……。自分のためじゃなくて、誰かのためになら、歌えるんじゃないのかな」
「誰かのため……ね」
.png)
そうつぶやき、窓の外に視線をやる。広がっていた雲はいつの間にか消え去り、視界には島の景色が広がっていた。
「誰かのために歌うなんて、考えたこともなかったな」
「今までだって、たったひとりのために歌ったことがきっとあるはずだよ」
果たして、そんなことがあっただろうか。私は常に、私のために歌っていたのではないだろうか。誰かのため、いったい誰のために? 私は力なく首を振った。
「だめ、ない。思い出せない。それに、歌を届けたい人なんて、私にはいないもの」
「そっか……じゃあ、ほら、あの人は?」
花譜が顎に指を当て考え込む。
「あの日、島に来たでしょう。白い服着た、AOの偉い人」
「リオ!?」
反射的に大声で問い返したが、花譜は意に介すことなく「そうそう!」と瞳を輝かせた。シュカも信じられない、といった表情をしている。あきれた私は大きなため息をつく。
「いや……あのね、花譜。どうしてよりによってあの男が出てくるのよ」
「正直に言うとね。私、リオのこと、よくわからないんだ」
「でしょうね、わからなくていいよ。ただの独裁者だよ、あんなやつ。AOから歌を奪った相手のために歌えっていうの? 冗談じゃない」
思わずそう吐き捨ててしまうぐらいには、体全体に嫌悪感が渦巻いていた。
「独裁者……見ようによってはそうかもしれないけど、でも、それだけじゃない気がする」
花譜の瞳が何かを探し求めるように揺れた。
「ねえノア。AOにいた人は、街から歌が消えてたことにすら気づいてなかったよね」
「うん。ケルビムで、歌の不在そのものに疑問を抱かないように誘導されていた……んだと思う」
記憶をたどりながら、そう推察する。私の歌を聞いた人がビーイングを外したのは、単にそれがAOの支配の象徴として皆に刷り込まれていたから。あるいは、市民の行動を操っているのがビーイングである、という考えこそがケルビムに誘導された思考なのかもしれない。考えていると、花譜の目が大きく見開かれた。
「でも、リオは歌を知っていた。あの人だけが、街に歌がないってことを知っていたんだよ?」
「そんなの当たり前じゃない。だからなんだっていうのよ」
「それって、すごくさびしいことなんじゃないかな?」
そう言って、花譜は窓に視線をやった。上空に静止している舟からの景色は、雲が晴れたことを除けばずっと同じだ。眼下の島のどこかにリオがいて、私たちの動向も把握しているに違いない。こんなところでリオの話をしている場合ではないのだが、と忘れていた焦りが急に襲ってくる。私は花譜の手を振り払って立ち上がった。
「花譜はリオをいやにかばうんだね。仮にさ、リオが歌そのものを憎んでるなら、さびしいどころかせいせいしてるかもよ?」
「ううん、そんなことない」
花譜はきっぱりと言い切った。
「リオが島に来たとき、言ってたよね。『君の歌は相変わらず素晴らしいよ、ノア』って。私には、本心からの言葉に聞こえたもの」
「本心ですって? 笑わせないでよ、だって」
ビーイングでみんなを操ってるって嘘ついてたじゃない——そう言いかけて、違う、と気づく。あの日リオが告げたのは、私にビーイングが着いていること、そしてAO市民は皆なんらかの役割を与えられているということ、それだけだ。第一、ビーイングで人々の行動を操っていると思っていたのは、私を含めた島のみんなだけ。リオは一言も、ビーイングで私を操っているとは言わなかったのではなかったか。混乱する私に、花譜がさとすように言う。
「ねえノア。歌を忘れちゃった人よりも、歌を覚えているのに誰も歌わない街で生きていくほうがずっとずっとさびしいよ。ノアにはシュカちゃんや、私だっている。でも、リオは?」
私は、島をひとりさまよっていたときを思い出す。光に満ちていく中、他人とわかり合うことも、傷つけ合うことさえできない、冷たい孤独。それを、リオはずっとひとりで背負ってきたというのか。そして、これからもずっと。自分の意思で、ひとりだけの世界で生きていくというのだろうか。彼のいう「調和」と引き換えに?
「そうか。リオも、選んだんだ……」
形のない何かを確かめるように、口に出してみる。今だって、AOのシステムが正しいとはとうてい思えない。リオが描く理想の世界など想像もつかない。それでも。
「どう、ノア。歌えそう?」
心配そうに尋ねるシュカの頭に、そっと手を置いて首を振る。
「それはわからない」
必ずまた歌えるはずだという、先刻までの希望は霧散していた。
「でも、リオに届けたい歌なら、ある……気がするんだ」
今までだって、たったひとりのために歌ったことがきっとあるはずだよ——さっきの花譜の言葉を反芻(はんすう)する。私も、誰かのために歌ったことがあるのだろうか。自分ではなく、誰かのために歌えるのだろうか。
「違う」
船内に響いた自分の声が、わずかに残っていた不安をぬぐった。声を取り戻したいから、リオのために歌うのではない。リオを自由にするためでもない。ただ、リオのためだけに歌いたかった。私の歌を受け取ったリオが、ケルビムによる支配を続けるならそれでも構わない。それも、リオの選択なのだから。
喉元に伸ばした手が、冷たい首すじに触れた。決めるのは、常に私。
「シュカ! UMDをもう一度起動させて。まだ呼びたい人がいるの」
*
誰かの呼ぶ声。はるか遠く、ここではないどこかから。吹きすさぶ嵐の中心で叫んでいるような声は途切れ途切れで、今にも見失いそう。でも、声の主は、確かに私を呼んでいる。応えるように目を開けると、眼前にノアがいた。
「ノア!」
叫んだ私に、歌姫はゆっくりと顔を上げた。首元にチョーカーはない。
「ノア、あなたもう……」
言葉じゃない何かが込み上げてきて、それ以上言えなかった。でも、尋ねなくたってわかる。今のノアは、リオの前で今までの自分を否定してみせた彼女じゃなかったから。こちらを見つめる自信にあふれた瞳は、私を舟にいざなったときのものだったから。それに、どこまでもエゴイスティックな目の奥に、以前とは違う何かが宿っているようにも見えた。ゆがんだ視界を、思わず手で覆う。
「よかった……」
「なんで泣くんだよ」
きょとんとしたノアは頭をかきつつ、大股で歩み寄って私の肩に触れた。がさつな所作と裏腹に、彼女の手のひらから伝わる穏やかな熱。
「声が、ノアの声が聞こえたの。私の世界にまで、届いたんだ」
「ああ、私があなたを呼んだ」
「私も、もう一度だけ会いたかった。AOに行かなくちゃ、ノアに会わなくちゃいけないと思ってたんだ」
意を決して、顔を覆っていた手を下ろす。ノアの背後には、皆もいた。花譜、森カリオペ、シュカ。みんな、私の言葉を待ってくれている。“外の世界”でずっと考えていたことが、口をついて出てくる。
「ノアに、みんなに、謝らないといけないの。あのとき、ノアがビーイングを壊したでしょう? 聞いて。あれは、私が。私がね……」
そこまで言った途端、言葉が出てこなくなった。私が、いったいどうしたというのだろう。元いた世界で、あれだけ後悔したのに。ビーイングを壊したことを……いや、違う。もう一度、何も着いていないノアの首すじを見る。そう、ビーイングを壊したのはノア自身だ。私は何をノアに伝えたかったのだろう。“外の世界”で、悔やんでいたのはなんだったんだろう。もしかして、UMDを通ってきた影響で忘れてしまった? そんなのないよ、だとしたら、なんのために来たのかわからない。
泣き出したかと思えば呆然(ぼうぜん)とする私に、ノアがどういうこと?と視線で周囲に問いかける。カリオペが肩をすくめて言った。
「よくわからないけど、ビーイングを壊したのはノアだよ。みんな見てたじゃない」
ノアもあきれたように続ける。
「当たり前じゃない……決めるのは、常に私なんだから」
私はうなずいて、笑った。ノアがノアを取り戻したのなら、今はそれでいい。ようやく落ち着いてきた私は、濡れた頬を袖でぬぐいながらあたりを見回す。全身に伝わる振動。舟だ──ここは、空なのだ。窓の外に、島が光っていた。
「あの光は……ケルビムね」
島全体を覆うケルビムの光は、上空から見るといっそう幻想的だった。温かい光に、私は初めてAOにやって来たときのことを思い出す。<ネクサス>の中を彩るケルビムに驚かされたのが懐かしい。思わず窓に近寄り、久しぶりの光に見とれる。
「ああ。だいぶ進んだ」
窓を見たノアが顔をしかめて言う。
「島全体がケルビムに覆われれば、私たちは本当に自由を失ってしまう」
ノアの言葉に、私は慌てて窓から飛び退(の)いた。
「どうして? ケルビムは関係ないでしょう、AOのみんなを操っていたのはビーイングだって、ノアも、リオも言ってたじゃない……」
だからこそ、ノアはビーイングを破壊したのではなかったか。しかしそう言いつつ、違和感は小さなものだけれど確かにあった。
「島には、ビーイングを着けた人はいなかった。でも、稼働しているケルビムもなかった……」
記憶をたどりながらつぶやく私に、ノアが大きくうなずいて言う。
「私につけられていたのは、ビーイングのプロトタイプ。それは本当だよ、リオが言ったとおりね。でも、みんなを操っていたのはビーイングじゃないんだ……」
ノアが低い声で話し始めた。チョーカーを失ったノアが、2か月も旧γ地区に隠れ住んでいたこと。島にケルビムが設置されるたび、人々の動きが変化していったこと。ケルビムの下では、誰もノアの言葉に耳を貸してくれなかったこと。ケルビムに魅せられたノアを、シュカが見つけてくれたこと。私が“外の世界”にいたときに起こったことの、すべて。
「導きの光」
私の口から漏れたのは、いつかのリオの言葉。あれは比喩ではなかったんだ。私がケルビムに魅了されたのは、その先進性だけじゃなかった、ということか。AOでの私は、いつもケルビムに導かれていたんだ——私はもう一度、こわごわと島の光を見た。それでもやはり、闇に映えるケルビムは、嵐の中の灯台のように思えた。固く目をつぶり、無理やり島から目をそらす。その瞬間、舟が大きく揺れた。私は思わず壁に手をつく。大きく上下する舟の中、歌姫は動じることなく立っていた。
「だから私は、最後に歌う」
最後。なんの最後だろうか。島の最後? 不吉な予感が脳裏をよぎるが、そんなの杞憂に決まってる。だってノアの歌は——
「島が、また自由を取り戻せるように?」
私の問いに、歌姫はきっぱりと首を横に振った。
「違う。私の歌はもう、誰の心も開かないかもしれない。だけど」
ノアはゆっくりと首に触れた。長い間、光を浴びていなかったであろう、白い首すじ。舟が体をもう一度大きく揺らし、下降を始めた。シュカが舟を島につけようとしているのだ。明るさを増してゆく窓の外の光を見ながら、ノアは、自分に言い聞かせるように口にした。
「もう一度、私が選びたいの」
*
静寂は一瞬。すぐに、かん高い駆動音が壁を伝って船体を震わせた。外壁が開き、迫(せ)り出してゆく。薄暗い船内にケルビムの光が差し込む。着陸した舟の周囲には、異変を察した人々が集まり始めていた。外壁は完全に開き、瞬く間に舞台となった。
花譜がうなずくと、ステージへと歩き出す。カリオペがこちらを一瞥し、後に続く。ぽっかりと空いた船体の向こう、赤と黒に明滅するケルビムの群れがこちらを照らしている。ノアは首に何かを巻きつけると、光のほうを向いた。歩き出すノアに、私は思わず叫んだ。
「ノア!」
振り向いた歌姫に、どなるように問いかける。集まった人々のざわめきに負けないように。
「あなたは、どうして私をもう一度呼んだの。……私は、何をすればいい? もう一度、この世界で」
わずかに目を開けたノアは、こちらを見てほほ笑む。きびすを返し、こちらに向かってくる。膝をついた彼女の首に、シュカが作ったチョーカーが光っていた。
「もうわかってるはず」
ノアは、私の頬をなでて、言った。
「この世界は、あなたたちの選択でできているの」
「選択……やっぱり。AOは並行世界なんかじゃない。“私の世界”、その未来の姿なんだよね」
「そうね、あるいは、ありえたかもしれない未来」
ノアの指がチョーカーに触れた。
「あのとき、あなたは選んでくれた」
そうだ。あのとき私は、ビーイングを壊すことを確かに選んだ。ノア、教えて。あの選択は、正しかった?
「忘れないで、決めるのは、常にあなたなの」
ノアが立ち上がって、言った。
「ありがとう。私を見つけてくれて」
そして彼女は、光に向かって進んでいく。
再び、この世界に来た意味。私は、AOの行く末を見届けなくてはいけない。選択の結果が正しいかどうかじゃない。ノアが、そしてリオが、何を選ぶのか、見届けなくては。私は残された船内で手を握った。
*
ケルビムはすべて、非常事態を示す赤と黒で点滅している。そのうち一基の映像が切り替わり、見知った人物の姿を映し出す。
「何かわかったみたいだね、ノア」
「いいえ」
意外な返答だったのか、画面の中でリオの片眉がわずかに上下する。
「気づいたの」
ノアは拡声器を通すことなく答えた。それでも、彼女の声は人々のざわめきを縫って一帯に響いた。
「私はずっと、自由だったってことを」
「わからないな。だから、再び歌うというのかい。その手に余る自由を振りかざして」
リオが諭すように言う。予想外の事態にも、相変わらず落ち着き払っている。舟の周りの人々が、ひとり、またひとりと輪を抜けていった。
「君の理想郷がどうなったか、忘れたわけじゃないだろう」
リオの優しい声音に、私はAOに来たばかりのころを思い出す。ネクサスから見えるAOの風景。おだやかな幸福に満ちた人々。くすぐったいようなせせらぎの音。理想郷──空疎にも聞こえるその言葉は、リオが発すると単なる理想論ではなくなった。リオが孤独だ、と感じた理由が今ならわかる。なぜならリオの楽園はこんなにも、ケルビムの光に満ちているのだから。
「島が変わっていくのをずっと見ていた。私たちが自由の名の下に失ってきたものは、こんなにたくさんあったんだって」
ノアはそういってあたりを見渡す。朽ち果てたステージなどどこにもない。整然と立ち並ぶ建造物、美しい水路、闇を照らすケルビム。あれからわずか2か月しかたっていないというのが信じられないほど、島は変わりきっていた。
「私にはできなかった。たったひとりとさえ、わかりあえなかったの」
後ろ姿のノアの肩が震えているように見え、私は不安になった。ケルビムの効果がどれほどのものかはわからない。でも、このままリオと話をさせておいていいのだろうか。いや、だめだ。逡巡(しゅんじゅん)する私の耳に、リオの優しい声が響く。
「それがわかっていながら、また歌うというの? 君はそれでいいかもしれない。唯一無二の才で人の心を打ち、時には涙を流させ、歌姫と祭り上げられるのは何物にも代え難い喜悦に違いないね。花譜やカリオペもそうだろう。しかし、そうではない者は? 歌いたくても歌えない者たちは、君の島でどうなった?」
畳み掛けるようなリオの言葉に、握りしめた手が汗ばむ。競い合うようにノアの寵愛(ちょうあい)を受けようとする者。理想と現実の間にそびえる壁に絶望する者。AOに帰してくれと懇願する人々。
「彼らを解放できるのはAOだけだよ、ノア」
「そうかも、しれない。私はこれからも、きっと誰かを傷つけてしまう」
歌姫の弱々しい返事に、私はもう飛び出す寸前だった。すんでのところで押しとどまったのは、彼女の手が首元に触れていたからだ。
「もう一度聞くよ……それでも、君は歌うというの?」
シュカの作ったチョーカー。ノアの手のなかで、いびつな石が揺れている。
「リオ。私は歌いたいんじゃない。自分で選びたいんだ」
「その選択が他人を傷つけるものであっても、かい?」
「ええ」
ノアの決意に満ちた答えに、花譜とカリオペも大きくうなずく。
「私は、私たちは、今この瞬間も、来たるべき未来を選びつづけている。選択によって未来は変わってきた」
「しかしそれは……」
ケルビムの中のリオは初めて見る表情をしていた。受け入れがたい何かを目にしたかのような、困惑の色。否定しかけたリオの言葉を、ノアが継ぐ。
「裏返せば、選ばれなかった未来がある、ということ」
ノアの言葉に、リオの表情が一瞬緩んだ。
「そのとおりだ、ノア。君が歌うことで、実現しえない未来がある」
「私の選択が、リオの理想郷を壊すというのなら……その痛みだって引き受けるわ」
「引き受ける? いったいどうやって?」
リオに答えることなく、ノアは群衆に背を向けこちらに振り向いた。ケルビムの中では、リオが小さくため息をついたように見えた。一瞬の後にリオの映像は消え、赤と黒の警戒色の点滅に戻る。
「花譜、カリオペ、シュカ。そして……あなたも。ありがとう、私についてきてくれて。私を、ここまでつれてきてくれて」
ノアと視線が交差する。私はうなずいた。私の選択も、誰かを傷つけるものだったかもしれない。それでも、見届けなくてはいけない。選ばれなかった選択肢のためにも。ステージの花譜、カリオペ、そしてノアが前を向いた。
「ねえリオ」
ケルビムの点滅が速くなった。
「今から、あなたのために歌う。あなたと、あなたの街のために」
ノアは左手で何かを掲げた。ゆがんだ枝に結びつけられた布。かつて島のあちこちにあったタペストリーを乱雑に繋ぎ合わせたそれは、かろうじて旗の体(てい)を維持していた。
「選ぶのは常に私。そして、あなたなの」
その言葉を合図に、舟が大きく震える。ステージを中心に広がっていく、力強い波紋。濁流にのまれた群衆の悲鳴も私には聞こえない。視界のケルビムもいつの間にか明滅をやめ、あたりは闇に包まれていた。今はただ、ノアの歌声だけがそこにあった。
fin.