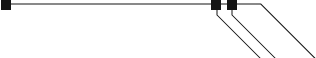「シュカは、どうしてノアのことが好きなの」
喧騒に覆われていた<島>もここのところずいぶん静かになり、α地区でさえ誰も歌っていないことがしばしばあった。暇を持て余した私がそう尋ねると、シュカはタペストリーを織る手を止め、はにかみながら言った。
「ノアは一回も、あたしの歌をへただって言わなかったから……」
「そう……なんだ」
それは誤解じゃないか、と私は思った。もちろん、心底うれしそうに言うシュカの前で口に出すことはなかったけれど。
シュカは確かに際立ってへただったが、ノアからしたらシュカも、かつてシュカをステージから降ろした人たちも、島の誰だって大差ないだろう。ノアは善意から指摘しなかったわけではなくて、本当にシュカの歌をへただと思ってないない。というより、なんとも思ってない。だって、歌姫は、自分が歌いたいから歌っているだけだから。花譜やカリオペは別としても、他人の歌なんてそもそも聞いていないのではないだろうか。
「それにね。あたし、前にもノアの曲を歌ってたの。うるさいとか、ノアのまねしないでとか、あんたはノアじゃないとか、たくさん言われたよ……」
と言いながらも、シュカに悲壮感はまったくない。
「そのとき、ノアが通りかかったの。みんな『この子、汚い声でノアの歌ばっかり歌ってる』ってノアに言うの。ノア、それ聞いてなんて言ったと思う?」
「そうね……シュカの歌はなんかこう、技術じゃ出せない味がある、とか? じゃなくて、努力にこそ意味があるのよ、みたいなこと、かな……」
言いながら、違うだろうな、とは思っていた。何より、ノアは自分を慕う少女に心ない言葉を投げかけられていても、そのまますたすたと歩いていきそうだもの。考え込む私に、シュカは笑顔で言った。
「怒りもせずに、『え? まねしたいなら、すればいいじゃない』って言ったんだ」
「なるほど」
それは確かに言いそうだな、と思った。模倣だろうと独創だろうとノアにとっては瑣末(さまつ)なことであり、すべて等しく価値がないのだ。ノアの軸は、自由かそうでないか、それだけ。
「だから、あたしが選ぶのは、いつだってノアなんだ」
シュカは織り終わったタペストリーを広げてみせた。あとで飾りにいこう、私は努めて明るく声をかける。島がきれいになったら、またノアも歌ってくれるかもしれないよ——。
*
ノアが歌わなくなって、何日が過ぎただろう、と私は川沿いを歩きながら考える。島から歌が消えかけた今、上空を舞う風さえ力をなくしているように思えた。シュカのタペストリーも力なく垂れ下がっている。今朝、β地区の住民がわざわざシュカ(と私)の住まいを訪れ、ノアに歌ってくれるよう頼んでくれないか、と懇願しに来た。
「無理だと思うよ」
シュカは困った顔で彼らに言った。私も同意見だった。誰かに頼まれて歌うノアはノアじゃないもの。β地区のみんなだって、自由を全身で体現しているノアだから、彼女に魅せられ島に来たんだろうに。なんだかすごく都合がいいことを言われた気がして、所在ないいら立ちを抱えたまま、シュカを残し私は外に出た。連日の雨で濁った川がごうごうと音を立て流れていく。
元から決して健康そうではなかったノアだが、歌わなくなった彼女は次第にやつれていった。
「歌うことは、ノアにとって生きることそのものだから」
シュカは心配そうにそう言った。以前の私なら、使い古されたセリフだと笑ったかもしれない。しかし、と私は濁流のしぶきを足元に感じながら思う。
島で聴いた、ノアの歌。彼女の強烈な自由への渇望が、聴くものを魅了しているのは明らかだった。彼女が歌うことをやめれば、ノアの胸でくすぶる熾火は内側から彼女自身を焦がし傷つけ、やがては。
「ノア、どうして歌わないの」
目の前の濁流に向かって問いかける。花譜やカリオペに歌ってもらえばいいじゃない、と一度、冗談めかしてノアが言っていたのを耳にした。まさか、嫉妬? そんなはずはない。だって、花譜とカリオペはノア自身が呼び寄せたのだから。リオが私を呼んだように……
「ごめんね。こういう話ができるのが楽しくて」
いつかのリオの言葉が頭に響き、私は顔を上げた。
「そっか……」
ノアは、歌を求める皆の声にずっとさらされてきたのだろう。島では自由の象徴として崇(あが)める声が途切れることなどなかったはずだ。ずっと皆がノアに耳を傾け、視線をそそいできた。だからノアは、花譜やカリオペを呼んだのかもしれない。自分と対等に見つめ合える人を。どこまでも自由なノアの孤独を、わずかでも分かち合える人を。自分の世界の遠く外側にいる人を。
ノアが私になぜ興味を持つのか、と不思議に思っていた。花譜やカリオペと違って、歌なんてろくに歌えないのに。
「私が、ノアを信奉していないから」
私はノアの歌を聴いて心を打たれはしても、ビーイングを壊しはしなかった。<AO>市民でないからなのか、ほかの理由があるのかはわからない。でも、私は外の世界の人間なのだ。元の世界、という意味ではなく、ノアを取り巻く世界の“外”にいる人間。だから、ノアは私を選んだ。
雨足が強くなった。私は川の向こう、ぼんやりと浮かぶAOの街を見つめていた。
*
「シュカ。明日、舟を出してくれる……」
夕暮れ時、γ地区にやって来たノアが言った。いつものように有無を言わさない口調だったが、どこか力強さに欠ける言い方で。
「明日って……出せるけれど。どこにいくの」
「歌うわけじゃないし、どこでもいいよ。βのみんなが帰りたいんだってさ。AOに」
川のせせらぎが虚(むな)しく響く。島では、誰ひとり歌わない日が次第に増えてきた。
「こんなつもりじゃなかった。こんなんだったら、AOのほうがいい、って。頼んでないのに島に来てさ、本当に勝手だよね……」
βの人たちは、AOに戻ることを決めたんだ。私はふたりのかたわらで思う。彼らが島にやってきたきっかけはノアの歌だったに違いないが、それでも自分たちで戻ることを決めたのだ。考えれば当たり前のことだったが、どこか意外に感じた。島の人たちは、ノアと一緒に朽ちていくものだと思っていたから。
「ノア!」
シュカの場違いな明るい声が響いた。
「わかった。あたしがみんなをAOにつれていく」
お願いね、というと、ノアはのろのろと立ち上がった。この島に来て1ヶ月と少しがたつが、歌姫の顔はずいぶんやつれて見える。ノアが歌わなくなって、2週間がたとうとしていた。
この島の生活は、奇跡に近いバランスで成り立っていたのかもしれなかった。いや、均衡などとっくに崩れていた。ありとあらゆるライフラインは欠け、壊れ、杜撰(ずさん)に扱われていた。このいびつな共同体が今日まで生きながらえてきたのは、ノアの歌があったから。皆が、ノアのほうを向いていたからだ。彼女の不健康そのものといった横顔だって、もしかすると、私が初めて会ったときからそうだったのかもしれない。でも、ノアがステージに立てば、そんなことは気にならなかっただけなのかもしれない。同じように、目を向けてこなかったことがたくさんあるのだろう。私はヒビの入ったままのガラスを見る。
「その代わり。舟を出す前に、歌って」
ドアを開きかけたノアが、動きを止めた。そのままこちらを見ずに尋ねる。
「どうして?」
「みんな、ノアの歌を待ってる」
シュカは努めて明るく振る舞おうとしていが、その声は震えていた。ノアは背を向けたまま微動だにしない。部屋に緊張が走った。そんなことで、ノアが歌ってくれるわけない。歌わないどころか、ただでさえいらついている神経を逆撫(さかな)でするだけなのに、と私はシュカを見やる。ノアは、ゆっくりとシュカに視線を向けた。その瞳には、氷のような冷たさが宿っていた。
「また、か」
ノアの声は低く、危険な響きを帯びていた。
「私は、私のためだけに歌う。何度も言わせないで……」
シュカは一瞬たじろいだが、すぐに笑顔を取り戻した。
「じゃあいい、歌わなくたって。歌わなくていいから、ノアもAOに戻ってよ」
「何言ってるの!?」
ノアの怒声に、シュカがひるむ。私も驚いた。シュカ、何を言っているの……
「歌えって言ったり歌うなって言ったり。挙げ句の果てに、AOに行けって?」
「お願い、ノア。AOに行けば、<ビーイング>を貸してもらえる。このままじゃノア、本当におかしくなっちゃうよ……」
シュカは目に涙をためて、ノアの両肩をすがるようにつかむ。
「AOで自由を失うのなら、ここでしんだほうがまし」
「もしノアが歌わないほうが幸せなら、あたしはその未来も守りたいの。でも、でも。そうじゃないでしょう」
「どうだっていい! あなたに守ってもらう未来なんてないから、シュカ」
ノアの痩腕で突き飛ばされたシュカが床に倒れ込み、私は慌てて駆け寄った。
「シュカ! ねえノア! ひどいんじゃな……」
肩を抱こうとした私の手が、シュカに振り払われたような気がした。
「シュカ?」
ひとりで立ち上がったシュカの目はもう涙に濡れてはいなかった。彼女は小さくつぶやいた。
「わかった」そして大きく息をつくと、
「ノアが選ばないのなら、あたしが選ぶ」
そう言って、棟を飛び出していった。シュカも、ノアも、もうおかしくなっている。いや、最初から、この島は正しくなかったんだ。それに目を背けてきただけのこと。私は決めた。明日、シュカの舟で一緒にAOに帰ると。
「ノア、私もβの人たちと一緒にAOに行く」
「…………」
ノアはシュカが出ていった扉の向こうを見つめていた。ずっと聞こえていたのは、川の流れる音ではなかった。開け放たれたドアから、雨音に混じって雷鳴が響く。
「ねえノア、聞いて。シュカは、あなたに歌ってほしいんじゃなくて……」
「じゃあ、何!」
何も言い返せなかったのは、ノアの剣幕に押されたからじゃなかった。私は気づいていた。シュカは、ノアに歌ってほしいわけじゃないんだと。その点で、彼女はこの島の住人と明確に一線を画していた。シュカは、ノアが好きなのだ。歌姫ではなく、ノアそのものを愛している。
始まりは歌だったかもしれないけれど。でも、それはシュカのひとりよがりだろうか。ノアは歌ってこそノアたりえるのかもしれない。周囲がどう思おうと、それは、ノアの中で確固たる事実。いや、本当にそうだろうか。それはノアにしかわからない。いや、ノアにすらわかっていないかもしれない……だめだ、全然わからない。私に理解できないことを、言葉にできるわけがない。
「歌が歌えたらいいのに」
口をついて出た言葉に、静かに驚いた。初めて思った。言葉にできないこの気持ちを、私の思いを、ノアに伝えられたらいいのに。リオとは短い間だったけれど、伝えたいことはなんだって湧き出てきたし、リオの描く未来にだって共感できたのに。どうして、ノアやシュカのことは何もわからないんだろう。私にも、歌が歌えたらよかった。私のつぶやきは、ノアには届いていないようだった。
*
靴底に、どこか懐かしい感触を覚える。外ではまだ、少ないながらも誰かが歌っていた。それなのに、ここには静寂があった。紙の束が、音を吸収しているのかもしれなかった。私は書架から適当に一冊の本を抜き出す。
「失われた時を求めて」
マルセル・プルースト。タイトルを口に出したとき、そうだ、と私は思い出す。<ネクサス>で、本を借りようとしていたことがあったっけ。慎重にページをめくろうとした途端、記憶の大河小説は砂になって指の間を流れていった。
旋律が聞こえたのはそのときだった。書架の間を縫うように遠慮がちに響いたその声は、周囲の空気と溶け合いながら、建物全体に染み渡っていくようだった。私は無意識のうちに、音の方向へ足を進めていた。たとえ暗闇の中であっても聴く者に恐れを抱かせない、慈愛に満ちた声だった。声の主は、入り口の石塊(いしくれ)に腰掛け、朝焼けに向かって歌っていた。ノアと共に歌っていた少女——私の姿を認めた花譜は、驚いたように立ち上がった。歌がやみ、私もはっと我にかえる。
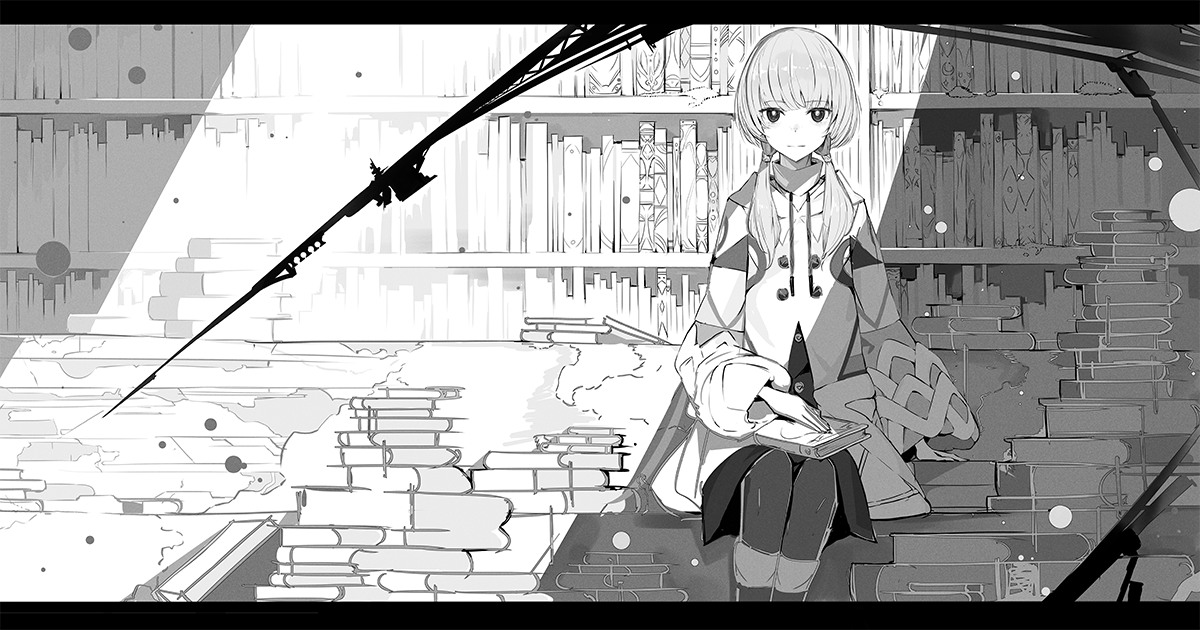
「えっと、あなたは花譜、さん」
「照れるな」
花譜がうつむいて下を向く。自信の塊のようなノアとは対極的な性格だ。
「花譜でいいよ!」
間近で見る花譜は、年もシュカと大して変わらないように見えた。この小さな体のどこから、あのような歌声が湧き出てくるのだろう。
「花譜。あなたも、ここではないところから来たんだよね」
「そうだよ。ずっと遠いところから来たんだ、ノアに呼ばれてね」
「私も、そうなんだ」
「同じだね。あ、パン食べる?」
ありがとう、と言って受け取る。
「花譜は、どうしてノアに呼ばれたの」
「歌を歌ってほしいって、あの子にお願いされたから」
順当な答えのように思えたが、それでもノアが誰かにものを頼む光景は思い浮かべられなかった。
「AOで見た。島でも、何度も聴いたよ。……すてきな歌だった」
「ありがとう、すごくうれしい」
花譜はそういってほほ笑んだ。言われ慣れているはずだったが、その控えめな笑顔は本心からのように思えた。その笑顔を見て、ふと思う。島にはたくさんの歌があふれている。でも、ノアのように歌える者はいない。彼女はたくさんの信奉者に囲まれた島でひとり、ずっと孤独だったのだろう。シュカも、もちろん私も、ノアの魂のひとかけらだって理解できていない。これだけたくさんの自分を慕う人たちに囲まれてなお、彼女はひとりだったのだ。
「あの……さ」
花譜がおずおずと口を開いた。
「ノアが歌わなくなっちゃったんだ。知ってる……」
私はうなずく。花譜はあたりを見回していう。
「この島は、ノアと共に生きてる。ノアが歌わなくちゃ、この島はみんなだめになっちゃう。私や、カリオペちゃんの歌じゃどうしようもできないんだよ」
「みんなは、ノアを求めているから……よね」
私の言葉に、花譜はうなずいた。
「みんな、ノアの歌声に引かれて、ついてきたんだよ。あなたも、そうでしょう……」