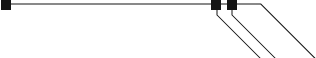四方から聞こえる歌声に、半ば無理やり起こされた。ネクサスでの心地よい目覚めとは天地の差だ、と私は天井の隙間から容赦なく差し込む日光に目を細める。粗末な寝具から体を起こし、壁に触れてみるが、何も変化はしない。わかってはいたけれど、でも落胆のため息が出てしまう。AOでは至る所に設置されていたケルビムはどこにも見当たらず、今触れているのもただの板だった。あたりを見回してみたが、部屋の主たるシュカの姿はなかった。どうしたものか、と私は壁にもたれる。
「ここではみんなやりたいことを勝手にしたらいい」
昨日、ノアはそう言った。やりたいことなんてないのだ、ずっと。でも、ただ膝を抱えて待ってるわけにはいかないのだろう、という確信もどこかにあった。意を決してドアに手をかけると、建物全体がわずかにきしむ。
外の空気は煙の匂いがした。匂いだけでなく、視界全体が薄くけぶっている。外にも見渡すかぎりケルビムは見当たらないから、照明代わりに火をたいていたのかも。AOとのあまりの落差に改めて驚く。ネクサスのあるエリアと、物理的な距離はそんなに離れていないはずなのに。
そして相変わらず、一帯は歌声で満ちている。私は歩きながら、風で揺れる旗を見上げる。ノアたちが島と呼ぶこの土地には小さなステージが点在しており、そのどれもがいかにも手作りといった粗末さだった。誰かが勝手に上がっては歌い始める。今にも舞台が崩れてしまいそうだ、とひやひやして見ていると、背後のステージからひときわ異質な声が聞こえてきた。振り向くと、人もまばらなステージの上で、シュカが歌っていた。私は足を止め、彼女の歌に耳を傾けた。

*
「あたしの歌、どうだった……」
ステージを降りたシュカが上気した顔で尋ねる。降りた、というか降ろされた、といったほうが正確だ。この島では、誰もがステージに立って歌いたがるものらしい。舞台はたくさんあるようだが、それでも歌い手のほうがずっと多いのだ。
「すてきだったよ」
「ノアみたいに?」
少し迷って、うん、と答えた。先ほどのシュカのステージで知ったのだが、この島に列や順番といった概念は存在しないようだ。今シュカと並んでいるこの配給でもそうだった。律儀に順を守っている私の前に、次々と人が割り込んでくる。
「ありがとう」
シュカが小声で言っている間に、また私たちの前に人が割り込む。私はうんざりして空を見上げた。さっき聞いたシュカの歌は、お世辞にも上手とはいえなかった。音程は常に不安定で、拍子は裏だったり表だったりを繰り返した。粗さの中に光るものがあるのでは、と思って耳を傾けていたが、なんの光も見いだせないまま、やって来た一団にステージを降ろされていた。ありていにいえば、かなりへただった。しかも彼女が歌っていたのはよりによって、AOで聞いたノアの歌。見物していた人の大半は嘲(あざけ)りを隠すこともしなかった。
「ノアも、島で歌うの?」
ここの住人にならって、私もノアたちの根城を「島」と呼ぶ。
「もちろん。最近はあまり歌わないけど」
そう言うシュカの指が、首元に触れた。ノアのチョーカーに似た首飾りが光っている。
ノアとおそろいだね、と言うと、うれしそうに顔を輝かせた。
「そう! ノアのをまねして作ったんだよ」
憧れの対象と同じものを身につけたい、という願望は、どこの世界も変わらないのだろう。昨日見た中にも、同じような首飾りをしている人がいた気がする。シュカの日に焼けた首筋を眺めていると、脳裏に白いノアの喉が浮かんだ。
「ふうん……シュカは、ノアが大好きなんだね」
私が言うと、少女は大きくうなずいた。
「あたしだけじゃなくて、島の人は全員ノアのことが好きだけどね。みんな、ノアの歌を聞いてついてきたんだから。あなたも、そうでしょう?」
「ええ」
「花譜ちゃんやカリオペちゃんも、すごくすてきだよ」
花譜、カリオペ。舟がAOに現れたとき、ノアと共に歌っていた人のことだろうか。聞き慣れない名前は、AOにもどことなくそぐわないように感じた。
「でも、AOの人たちをビーイングから自由にするのは、ノアの歌じゃないとだめなんだ」
シュカはどこか誇らしげに言う。原理はよくわからないが、ノアの歌はやはり特別な何かがあるのかもしれない。花譜やカリオペだって、私にはノアに勝るとも劣らない歌声に聞こえたし。
ん、ということは……
「ビーイングを自分で壊せなかったのは、私が本当のAO市民じゃないから、なのかな」
思わず漏れたつぶやきは、群衆の歓声にかき消された。
「ノア!」「ノアだ!」「ノア! 歌ってくれるの!?」
怒号のように繰り返される歌姫の名前。シュカが目を輝かせ指さした先、前方すぐの粗末なステージにノアが立っていた。押し寄せる群衆に囲まれ、瞬く間に身動きが取れなくなる。先刻まで人もまばらだったのに、どこから聞きつけて集まってきたのだろう。困惑する私に、観客のひとりが叫んだ。
「γで歌うなんて珍しいじゃない、ノア!」
「どこで歌ったって私の勝手でしょ」
ノアはすげなく答える。島の事情はわからないが、今にも崩れそうな舞台は確かに、歌姫には似つかわしくないな、と私も思った。
「選ぶのは、常に私なの」
そう言うや否や、ノアは歌い始めた。
*
曲の途中にもかかわらず、ノアはステージを降りた。未練がましく見守っていた人々も、ノアに再び歌う気がないとわかるや波のように引いていった。先刻まで漂っていた熱気が住民と共に消え去った今、あんなにまばゆく見えたステージも、ただの木片の組み合わせでしかない。ノアが歌っていたのは数分、いや、数十秒に満たない時間ではなかったか。しかし今もなお、ノアの歌声は頭蓋の中で響き続けていた。
「……すごいね」
絞り出した言葉はかすれていた。シュカの目は潤み、ほとんど泣いているように見えた。
「でしょう? α地区……島の真ん中の大きなステージで歌うことが多いから、こんなとこで歌うのはなかなかないんだよ」
隣にいるはずのシュカの声が遠く聞こえる。
「シュカや島のみんなが、ノアに引かれる理由がわかった気がする」
胸に手を当てると、ノアの声がいまだそこでとどまり熱を帯びているのがわかる。何より驚いたのは、昨日ビーイングを壊したノアと、ステージの上のノアがまるで違って見えたことだ。どちらも自分本位で利己的で、他人を顧みないところは変わらない。しかしその身勝手さが喉を通して放たれたとき、ノアの生命はまぶしいほどに輝いていた。くすぶる熾火(おきび)が、風にあおられ自由に燃え盛るように。天を突く炎の形が、誰にも予想できないように。
「自由、か」
「どうしたの?」
熱っぽい頭で考えていると、シュカが心配そうに顔をのぞき込んでいた。
「そっか。ノアは、どこまでも自由なのね。だから、私たちは……」
何を当然のことを言っているのだ、というふうに、シュカが首をかしげる。
「ううん……ごめん、うまく言えないな」
私は首をゆっくりと振った。配給の食事はとうになくなっていたが、この高ぶりの前では大した問題ではないように思えた。
*
島は大きく3つのエリアに分かれており、私が居候しているシュカの住居は島東端の外れ、γ地区に位置していた。α地区はノアや花譜、森カリオペがしばしば歌うステージが立っていることもあり、連日たくさんの住民が集まっているらしい。片やγ地区一帯は常に人もまばらだった。来た当初はなんて騒がしいところだと辟易(へきえき)したものだが、島の中ではこれでも閑静なほうらしい。
島に来て2週間がたった。ここでの生活にも慣れた私は、何度かシュカとα地区まで足を延ばした。ノアたちが拠点としていることも影響しているのか、点在するステージもγ地区のそれより格段に豪勢なものに見える。人々は活気に満ち、より力強い歌声にあふれていた。
そんな中、雷鳴のように響いたのがカリオペの歌声だった。暗雲を裂き沈黙すらも怯(おび)えさせる、ひと筋の強く美しい閃光(せんこう)。ともすれば無秩序すれすれの危うさをはらんだノアとは異質の、混沌と戯れるようなしなやかさ。
「こういう人が、ノアと並んで歌えるんだなあ」
シュカが心底うらやましそうに言う。
カリオペに促され、続いて姿を現したのは花譜だった。狂騒の残滓(ざんし)が残る舞台に進み出た彼女は、小柄な背丈も相まってひどくはかなげに映った。しかしそれは一瞬のことで、小さな唇がつむぐ詞は湖面に落ちた雨粒のごとく、胸の深層に穏やかな波紋を広げていく。舞台から同心円に広がるさざなみが、花譜の意思と同調するように重なり、溶け合い、混ざり合う。それはいつしか巨大なうねりとなり、世界にひそむ名もなき湖まで震わせていった。
「花譜ちゃんもすてき。やっぱり、ノアが呼んだ人に間違いはなかったよ」
「ノアが、呼んだの?」
はしゃぐシュカに、思わず聞き返す。利己主義の塊のようなノアが自ら、花譜やカリオペのような歌い手を招いたというのが解(げ)せなかった。そして何より——
「歌を失ったAOに、花譜やカリオペみたいな人たちがいるなんて」
「AOじゃないよ。“外の世界”から呼んだんだ」
背後から聞き慣れた声が聞こえ、思わず振り返った。
「ノア!?」
「UM……なんとかっていう装置を、まあちょっと拝借して」
いつの間にか背後にいたノアは、悪びれもせずにそう言った。無造作に散らかった頭髪、飾りけのない黒い衣服。相変わらず、歌っていないときの彼女はごく普通の少女だった。肌は白いというより不健康そうな青白さで、生命力の発露のようなオーラは微塵(みじん)もない。その証拠に、ステージを囲む人々はほとんどノアに目を向けていなかった。
「あっ、ノア! ノアも歌う?」
「今は気分じゃないの」
シュカが残念、と唇をとがらせる。そんなことより。
「<UMD>ね。ニュースで見たよ。あと、返さないのは拝借とは違うよ」
私はつい詰問口調になる。どうもAOの人たちは、他の世界から人を呼ぶことにためらいがないらしい。
「ねえ、あなたさ」
ノアは私の質問を無視して言った。漆黒の瞳で、私を見据えて。
「ちょっと付き合ってよ」
*
夕方のγ地区。川沿いを私はノアと共に歩いていた。ノアだけではない、後方にはなぜか花譜とカリオペ、シュカもいる。
隣を行くノアは口を開かず、ずんずん歩いた。ちらと横顔を見たが、真一文字に結ばれた口からはなんの感情も読み取れない。島の人たちに声をかけられても、「今日は歌わないから」とそっけない。シュカは憧れの歌姫ふたりに挟まれて上機嫌なようで、後ろからは楽しげな話し声が聞こえる。気まずくなった私は、上空にはためくタペストリーを指さした。
「これ、シュカが作ったんでしょ。上手だよね」
「ん? ああ……」
「シュカは手先が器用なんだね」
「舟も、シュカが一番うまく飛ばせるんだ」
そう言ったきり、ノアはまた黙った。
ノアの首元でチョーカーが光った。黒曜石のような、鋭く黒い光。
「それ、島の人たちも似たようなのつけてる」
ノアはあきれたように笑って、後ろのシュカをちらと見た。
「小さい頃、まねするしないでケンカになったこと、ない?」
「ある。私はどちらかといえば、まねするほうだったけど」
だろうね、とノアが皮肉げに言ったので少しむっとする。こっちは気を使って話題を提供しているというのに。そもそもなんなのだ、この時間は。しかしノアはそんな私の気も知らず、
「見た目だけまねても意味ないと思うけどなあ。そうじゃない?」
「どうだろう……ノアのそれは?」
「つけてると安心するんだ」
ノアはさらりと言ったが、少し引っかかった。安心。嵐のようなノアの歌声と、その単語がスムーズに結び付かなかったのだ。ノアは左手でチョーカーをもてあそんでいる。鉱石のようだが、継ぎ目や留め具は一切ない。装飾品にしては武骨すぎるけど、ノアには不思議となじんで見えた。
「ノアの歌は、どうして人々を自由にするのかな」
「あなたは違うでしょ。あなたはビーイングをつけたまま島に来た」
「……でも、ノアのおかげで歌を思い出すことができた。AOでは、歌を忘れてたってことさえ、思い出せなかったから」
必要もないのに、弁解じみた口調になってしまう。
「ねえあなたさ、舟で来たとき、リオって言ってたよね」
ノアの口から出た名前に、胸が少しだけ痛むのを感じた。
「それは……」
「別に責めるつもりないから。それより、聞いてほしいことがあってね……」
*
アルカの民、って知ってる? 知ってるわけないか。
同じ国の人でも、見た目が一緒でも、遺伝的ルーツっていうの? そういうのっていろいろあるじゃん。私はアルカの民の血を引いてるんだ。外見はほぼおんなじだけどさ、この髪の色とか、AOでは見なかったんじゃない?
まあいいや。でさ、人類が言葉で意思疎通を図る前って、何を使っていたと思う? 歌なんだって。でも、言葉ができて、歌のコミュニケーション能力は失われていった。当然だよね、尻尾みたいなものさ。使わないものは次第になくなっていく。あっても邪魔だからね。
でも、ときたま、尻尾を持った人間が生まれることがあるでしょう。アルカの民にも、ほかの人々とは違う特徴があった。なぜだか、その失われた遺伝的因子を持っていたんだ。難しいことはよくわからないけど、リオたちがそう言ってた。
どうしてリオが出てくるかって? リオたちは、街のシステムに、私たちアルカの民の力を使おうとしたらしい。今はもう覚えてないけど、何か機械を付けられて、歌わされたりしたな……。いや、別に非人道的なことをされてはいないよ。よくわからないけど、私たちが持つ、非言語コミュニケーション能力を解析して、まったく新しいシステムを作ろうとした、って聞いてる……
*
「そうなんだ」
われながら間の抜けたあいづちだと思いつつ、のみこめたのは話の輪郭に過ぎないのだろうな、とも感じていた。ノアが計画に参加していたのはずいぶん前のことみたいだから、彼女自身も複雑な計画の全貌を把握してはいないのはわかる。ただでさえ、AOの元となったシステムなのだから、根本から理解するのは難しいはずだ。それよりも。ステージではあんなに雄弁だったノアなのに、言葉での意思疎通が不得手のようだった。そのギャップが、ところどころで私の理解を妨げる最たるものだった。あるいは、リオの理路整然とした語り口に慣れていたせいかもしれない。
「どうしてこんなに話してくれるの?」
しかし、悪い気持はしない。ノアがここまで個人的なことを話してくれた喜びはあった。そして同時に、なぜ相手が私なのか、という疑問も。
「別に。なんとなく話したかったから」
「そのシステムは、どうなったの」
「失敗したんじゃない? 私も、一緒に参加していた人たちも、その後は知らされてないみたいだし」
「歌を使った調和なんて、とてもすてきなのに。どうしてだめになっちゃったんだろう」
「はあ? そんなこと知らないよ」
話しておいて、こちらが乗ってきたら突き放される。しかし、ノアを見ていたら失敗した理由もなんとなくわかる気がする。歌のシステムに見切りをつけたリオが、別の方法で調和を目指した。それが、ビーイングということなのだろうか……。
「調和、ね。本当にそんなものがすてきだと思う?」
後方から投げかけられた問いに、私は足を止め振り返る。すらりとした体躯に、わずかだが周りを圧倒する雰囲気をまとった声の主――森カリオペだった。私は戸惑いながら答える。
「AOは……いい街だったよ。平和で、清潔で、みんなが互いのことを思いやっていたもの」
私は記憶をたどりながら答える。自然豊かな街を、ケルビムが彩る都市。外面だけではない。島のように、いらないものを地面に捨てていくことや、技術の足りない者をあざ笑うこと、それに順番を守らないなんてことはAOではありえなかった。というより、AOでは行列そのものがなかった気がするけれど。
「私がAOにいたのは少しの間だったけど……それに『調和』っていっても、誰かに強制されてそうしてるわけじゃない、自由だって」
「でも、歌がないんでしょう。おかしいとは感じなかった?」
黙り込んだ私に、カリオペは続けた。
「皆が皆、したいことをやって、社会が円滑に進んでいくなんて、そんなことはありえない。何かを得るには何かを手放さなくちゃいけない。誰かとぶつかるときだってあるはずよ。私だってノアだって、そうやって生きてきた。花譜もそうでしょう……」
カリオペの視線を受けた花譜が小さくうなずく。太陽はいつしか沈み、水辺と地面の境目もよくわからなくなっていた。