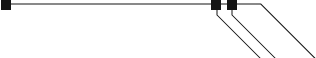「すてきな街!」
「そう言ってもらえるとうれしいな」
そう答えるリオの表情には、社交辞令ではない誇りと自信が見てとれた。
「なんて美しい街なんだろうって思ってたの。早くここを歩いてみたいって」
そのために慣れないトレーニングも頑張ったんだし。と私は、はやる気持ちを抑えられなかった。この軽くなった体で、今すぐ駆け出したいぐらい。
外で見上げるネクサスは思っていたよりずっと巨大で、周囲の建物や駅とおぼしき施設と麓(ふもと)でつながっている。有機的に絡み合う構造物の隙間には、多種多様な植物が群生し、小規模な森がそこかしこにあった。
「そして、静か……」
都市運営の中枢を担うネクサスがあるのだから、ここはAOの中心地に違いない。事実、駅に向かう人、広場でくつろぐ親子、視界ではたくさんの市民が思い思いに過ごしていた。滑るように道路を行くモビリティの横を、自転車が軽快に走っていく。ネクサスにもたくさんの人が出たり入ったりしている。それなのに、心地のよい静寂があたりに満ちていた。
ネクサスの中で私を驚かせたケルビムは、AOの街でもやはり目を引いた。それは単なるモニタとしてだけでなく、信号、標識や掲示物など、視覚情報の出力装置としてのあらゆる機能を担っているようだった。目の前のビル群も例外ではなく、壁面を覆うケルビムがさまざまなビジョンを映し出している。気候に合わせて構造物表面のケルビムを変化させることで、空調を使うことなく内部の温度調整も可能だという。
「きれいな街ね。でも……潔癖とか、無機質っていうのとも違う。なんだろう、ぴったりくる言葉が見当たらない……」
リオの説明が一段落すると、耳に入ってくるのは、木々のざわめきや、行き交う人の穏やかな話し声。どこかから、川のせせらぎすら聞こえてくるようだ。元いた世界の街とは明らかに異なる何かが確かにあったが、それを言い表すのは難しかった。ちらとリオを見ると、優しげな微笑でこちらを見つめている。その表情に、私の答えへの期待を読み取るのは考えすぎだろうか。ひとさじの緊張をはらんだ、優しい静けさ。元いた世界でも、私はよく似た感覚を知っているはず。
「図書館……街全体が、大きな図書館みたい」
私のつぶやきに、リオの声が少し明るくなる。
「なるほど。詳しく聞かせてくれるかな」
「静寂、ってだけじゃないの。図書館って、いろんな人が、別々のことをしているでしょう。みんな本を読んでるんだけど、それぞれ違う本を読んでるよね。それに、勉強する人もいたりするし……」
私のたどたどしい説明を、リオは何も言わずに聞いてくれている。
「確かに同じ場所にいるんだけど、でも、それぞれ自分の世界にいる、っていうか」
「それぞれの世界。例えば、物語の世界のことだね」
「そう。それに、同じ本を取り合ったりもしない。読もうと思っていた本がなければ、違う本を読むしね。静かに同じことをしているようで、本当はみんな違うことをしている人たち、その集まりが形づくる空間……そういう、心地いい場所が浮かんできたの。うまくいえないんだけど……」
「本が好きなんだね」
私は無言でうなずく。本は好きだ。物語の導きは、私に選択を強(し)いないから。
「ねえ、本が一冊しかない図書館があったら、どうかな。それでも図書館だと思う?」
「何それ……そんなわけないでしょう」
「そうだね。じゃあ、たくさんの本だけがあってたったひとりしか利用者がいなかったら、どうだろう。あるいは、同じ本がたくさんあったら、それは図書館かな」
本だけあって人がいないなら、それは書庫だ。同じ本ばかりあったら……そんなの意味はない。いろんな本があるから、いろんな人が来るんだもの。そう考えると難しい。図書館が図書館たりえるための、必須条件。さまざまな本があること。そもそも、本ってなんだっけ? 紙に書かれた文字、情報。何百年も前から紡がれる物語、体系化された知識。それぞれが異なる無数の何かが一体として成り立つために必要なもの。分類。秩序。調和。
「調和……?」
ふと漏れた私の言葉に、リオの表情がほころんだ。
「いい言葉だね。そう、ここでは、すべての市民がとても自然に、そして無理なく秩序を保っている。調和して暮らしているんだ」
私は光や音、自然や人工物の融合を指して言ったのだったが、リオの声ははずんでいた。
「人が調和している? 街やモノがじゃなくて?」
尋ねながら目を落とした足元で、水流が光を乱反射する。
水路といえばいいのだろうか、白く硬質な小路に沿って水が流れており、せせらぎはここから聞こえるようだった。幅1mほどの水路は街のあちこちに設置され、葉脈のように分岐を繰り返しているらしい。水路が交わる地点で勢いを増した水の音が、街路樹がゆれる音や子供のささやかな笑い声と重なり耳に届いた。リオが視線を向けると、3歳ぐらいの幼児がこちらに向け手を振った。
「そのとおり。君が感じている街の調和は、人々の調和なくしては生まれないものなんだ」
人々の、調和。私はあたりを見回す。行き交う人は皆、前の世界にいたときと変わらないように見える。リオの真意、そのヒントを街に見いだそうとしている私に、
「人々の調和を目で見ることは難しい。見えるのは、それが乱れたときだけ……」
リオは幼児に手を振り返しながら言葉を紡ぐ。その子の左腕にも、乳白色の腕輪が光っていた。
「君は、街の様子を通してAOの調和を感じ取った。それはすごいことだよ。街が君を選んだのは間違いじゃなかったんだね。元から僕はそう確信していたけど」
リオははずんだ声で再び歩き出す。意図した答えとは違ったのだが、彼に褒められて悪い気はしなかった。
「人の調和、かあ」
とはいえ、少々拍子抜けだった。今までに感じたことのない、静謐(せいひつ)で心地のよい都市。さぞかし先進的な技術やシステムが働いているのだろうと思ったが、そうではないらしい。足を止めると、水路の水がケルビムの光を反射してきらめく。よく見ると、街のシンボルのように張り巡らされている水路は、ただの溝ではなかった。
「面白いね、この水……」
両側を芝生で挟まれた白い路は、水流に磨かれ鈍い光沢を放っている。路の表面に明確な溝はなく、目を凝らすとわずかなくぼみが見てとれた。くぼみに導かれるように水は曲がり、時に広がり、また細くすぼみながら流れている。くぼみは形も深さも一定ではないようで、水は時折路からあふれそうになりながら、しかし一滴も漏れることはなかった。私は感心して息をつく。石の路と流れる水、静と動、硬いものと形のないもの、永久と刹那。相反するものが一体となって織り成す光景はまるで調和の象徴のようで、街中の水路はAOのシンボルなのかもしれない、と私は思った。流れゆく水は時に緊張感をはらみながらも、迷いなく行き先を知っているようだった。
「ケルビムやビーイングも見飽きないけど、この水路もずっと見ていられそう」
私はふと、しゃがみこんで水に触れた。流れる水が、指先の温度をさざなみを立てながら奪っていく。だが、手を水の中に浸しても、その流れを変えることはできなかった。わずかに抵抗を感じるだけで、下流の水にはなんの変化も見てとれなかった。
「思ったより冷たい。指の先が変な感じ……」
背筋がぞわっとしたのはそのときだった。指先に伝わる冷気とは違う。視線? 私ははじかれたように立ち上がった。公園を行き交う人たちは、さっきまでと変わりない。息をはずませるランナー、自転車をこぐ人、ベンチで何かを読んでいる老人。誰も私のことなんて見ていない。なんだったんだ、今の寒気は。

行き場のない視線を下ろすと、足元で芝生がつぶれている。水路の周りはきれいに刈りそろえられた芝が敷かれていたのだが、私はそれを踏んでいた。ぎょっとして足を上げると、芝がめくれ黒い土が露わになる。視界の中、芝生に突っ立っているのは私だけだった。汗がにじむのを感じつつ、小走りでリオに駆け寄る。
「だって、芝生に入っちゃいけないって書いてなかったから……」
さすがにばつが悪くなり、リオ相手に意味のない言い訳をしてみるも、彼は微笑してこちらを見つめるばかりで、何も言わない。恥ずかしさも相まって、私は思考の整理もつかないまま言葉を吐き出した。
「なんか、今ぞわっとしたの。私が調和を乱したから、なのかな。誰かに見られたような……いや、誰も見てはいなかったんだけど」
気のせいだろうか。もう一度あたりを見てみても、やはり誰も私のことを気にも留めていない。水路を振り返ると、芝生は確かに足跡の形に乱れている。やはり錯覚なんかじゃない。だって、あの見とがめらるような感覚がなければ、私はまだあそこに座って水路を眺めていたはずだもの。だとしたら、誰に見られていたのだろう。
「まさか、街?」
相変わらず凪のような静寂だったが、それも今は空恐ろしく感じられた。元いた世界では、街で人の声や木々の葉がすれる音なんて感じたことはなかった。代わりに聞こえてきたのは、車のクラクションや、電車の音、そして……なんだっけ、思い出せない。でも、元いた世界の猥雑さがなぜだか少し恋しくなった。首をひねる私に、リオは笑っていった。
「AOは前時代的な管理社会ではないよ。僕たちは自然で水路を整備しているだけで、あとは流れを変えるようなことも何もしていない。流れるままに任せている」
「水路を整備、ね。いいように言うけど、みんなを同じ方向に向かせてるってことじゃない?」
さっきの、言い表せない怖気のようなもの。あの冷ややかさを感じる前と後で、私の中のAOに対する感情が180度変わってしまったかのようだった。棘(とげ)をはらんだ私の質問に、リオは笑って言う。
「まるで逆だよ……この水路だって、別に真っすぐ整備されているわけじゃない。緩やかに曲がって、幅を変えて、それはすべての瞬間に水が自由に流れることを認めている。争いはむしろ、皆が同じ方向に流れようとするときに起こるんだ」
「それこそ逆じゃない? みんなが同じほうに流れていれば、ぶつかったり、いさかいになることなんてないと思うけど」
「君は、この水路に触ってみて何を感じた?」
「え? ああ、そうね……」
私は濡れた手のひらを見つめる。指をすり抜け、自在に、生き物のように街を巡る水。
「自由とか、循環。あるいは生命……かな」
「AOのシステムは、流れゆく水とよく似ている」
服の裾で手を拭きつつ、リオの声に耳を傾ける。
「この水は、水路に沿って強引に押し流されてるわけじゃない。自然の成り行きで、でも確実にこの形を保って流れていく。AOの人々も同じだよ。みんなが自由に生きて、同時に、この調和が生まれてる」
「AOが、水路。人々が、自由に流れる水、というわけ」
「そう。AOは、市民という水の流れを補助する岸壁に過ぎない。でも、この岸壁は水の流れに沿ってデザインされている。市民を動かしているのは、あくまで彼ら自身なんだ」
白く伸びる水路が、ケルビムの40階から見下ろすAOの景色と重なる。
「皆が自然に、望むままに、そして調和して動く。それぞれが自分の役割を理解し、他者を思いやる。それはまるで……」
適する言葉が見当たらなかったのか、珍しくリオが口を結んだ。まるで、なんだろう。個々が異なる役割をこなすことで成立するもの。それらの役割が織り成す調和から生まれるもの。そういうものが、確かにあった気がするのだが。考えを巡らせてみるが、リオが考えあぐねている問題に私が答えを出せるはずもない。早々に思考を切り上げた私は、水面に映るAOを眺めた。リオの言葉が頭の中でゆっくりと沈殿していく。完璧に見える街並みの向こうに、何か複雑な仕組みが隠れているような気がした。でも、それを深く追求する気にはならなかった。穏やかに流れる水のように、私の疑問も自然と消えていく。リオは、遠くきらめくケルビムを眺めて目を細めた。
「混沌とした外の世界は、岸壁のない水路のようなものだよ。氾濫する濁流も、真っすぐ固められた水路も、調和とは程遠い」
私は水路を見つめる。不定形な水の連なりから生まれる、美しい流れ。
「AOでは人と社会の調和がデザインされているとも言える。ここでは誰もが自分の意思で行動しつつ、他者を思いやることができるんだよ……」
リオは再び歩き出す。彼の進む先には、大きな噴水があった。それは一体のエリアを流れる水路の根源でもあるらしく、噴水に近づくにつれ、白い水路が束ねられるように合流を繰り返し、せせらぎの音が重なり合っていく。
「秩序のない水の流れは自然の脅威の最たるものだよね。僕は人間だって同じだと思う。水路という枠に収まらない水は、ひとたび氾濫すれば大惨事になる。無理やり流れを阻(はば)めて収めてもいけないし、流れて土地を削るままに放置していてもいけない。君がいた社会では、思想の違いは争いの火種になっていなかった?」
「異なる思想を許さない社会もあった」
「そうだろうね」
リオの視線が遠くを見た。AOの外に思いを馳せるように。
「この水路の水はとても自由に流れている、そこになんの統制もありはしない。そして、流れ続ける限り涸(か)れることもない」
「でも、ずっと昔。それこそ社会ができる以前、人類はもっと自由だったんじゃないの?」
「人々が自由であることは対立を生むこともある。実は僕たちの寛容さは無限ではなかった。分断から対立、紛争へとつながっていった。それに対して権力を生み出して統制しようとすれば、個人が失われていった。君の言う社会もそういうモデルだね。AOの外ではどちらの社会も現役だよ。人々は虐げられ続けていると僕は思う」
「そうね。私の世界……“外の世界”も、そうだった」
「それらを乗り越えるための方法を見つけたのが、AOなんだ」
「その答えが調和、ということなの」
私は立ち止まり、リオの瞳を見つめた。さっきまでのほの暗い不安はとうに消えていた。リオはうなずいて続ける。
「もう少しここで過ごせばわかると思う。AOでは、自分を無理に変える必要はない。ただ、自然に流れに身を任せていればいいんだ」
「流れに、ね……」
「ここは昔から水の都市なんだ」
リオがそう言ったと同時に、噴水から上空へ、一本の水流が噴き上がった。
周囲の人々の視線が集まり、私も上方を見た。10mほどの高さまで舞い上がった水の塊は上空ではじけ、光の粒子となって降り注ぐ。私は日差しに手をかざしながら目を細めた。