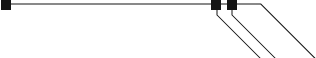柔らかな日差しを感じ、自然と目が開く。天井一面に広がる青空。この部屋、そして都市<AO>で迎える十数度目の朝だ。目覚めたときの光景に驚くことはもうなくなったけれど、かといって見飽きることもない。むしろずっと眺めていたかったが、壁面の空に現れたウインドウを見るため体を起こし、ついでに伸びをした。ウインドウにまとめられた今日のスケジュールや気象情報、ニュースのヘッドラインなんかを流し見しつつ、支給された服に袖を通す。日替わりで届けられる衣類は清潔で新品のようにぱりっとしているのに、身につけた途端肌になじむことに日々感心する。頼めば、この街を出るとき何着かくれたりするだろうか。帰ることを望めば、の話だけれど。
着地点のない考え事をしつつ着替え終わる頃にはウインドウは消え、壁は地上の街並みを映し出していた。先ほどのスケジュールによれば、昼食後にはリオが来る。そう思うと、眼下の街並みがさらに輝きを増したように思える。それまで何をして過ごそう? 現状、私に許された自由は40階の1フロアのみだったが、それでもまだ探索できていないところがたくさんあるのだ。
ここは都市AOの中心に位置する、<ネクサス>の高層フロア。街全体が“一望”できるなかなかの眺めだが、もちろんここは私の家じゃない。ある日、まるでなんの予兆もなく、私はこの一室で目を覚ました。突然の事態に混乱する私は、あらかじめ待機していたとおぼしきネクサスのオペレータらに“保護”され、以後ここで穏やかな日々を送っている。与えられた部屋は以前の住まいとは比べ物にならないくらい快適だし、何より——
「これが、窓じゃないだなんて」
壁一面の光景に、そっと触れてみる。指先から波紋が広がるように外の景色が消失し、空灰色の壁が現れた。指の腹に伝わる感触も数秒前のつるりとしたものではなく、わずかに粗さを残して磨かれた鉱物のよう。先刻の景色も空灰色の壁紙も、壁面に設置された情報投影膜——<ケルビム>が映し出した映像であり、質感の変化は触覚提示技術のなせるわざだという。しかしどれだけ凝視しても、目の前に映し出されているのが映像だなんてわからなかった。もう一度触れると、壁は再びAOの景色を映し出した。
わからないことは山ほどある。ネクサスとは、AO全域の管理および運営を担い、市民の生活に関するあらゆる施策の策定を実施する機関である、とオペレータのひとりが以前説明してくれた。似たような機関については私も覚えがあったが、私はどうしてそんなところの一室をあてがわれているのか。支給される服の素材も初めて触れる質感だし、オペレータが日々届けてくれる料理は見たことのない形状のものばかりで、時折、謎の食材が混じっていることもある。昨夜こわごわ口にした飲み物なんて、お茶なのか果汁なのかすら判然としなかった。なのに私向けに作られたみたいにしっくりくる。なんという飲み物だったか聞いておけばよかった、と思いながら冷蔵庫を開けると、そこに数本、くだんのドリンクが用意されている。日常のサポートをしてくれるオペレータが配慮してくれたのだろう。私はキャップをひねって口をつける。相変わらずおいしい。何も書かれていない空灰色の容器は宇宙食みたいだ。
とにかく今、私にわかることはふたつだけ。ここはAOと呼ばれる都市が存在する、私のいた世界とは別の世界である、ということ。そしてもうひとつ。
「AOへようこそ。君のことをずっと待っていたよ」
初めて会った日の、リオの言葉。私がこの世界——この街に連れてこられたのは偶然ではなく、どうやら何かしらの理由があるらしい、ということ。
「ん、これって何もわかってないのと変わらない、のか……?」
至極まっとうな懸念が首をもたげかけたとき、公園を軽やかに駆ける男女が窓越しに目に入った。今まで運動の習慣なんてなかった私だけれど、あんな緑の中を走るなんて気持ちが良さそう。いつか、外に出られたら……。
「そうだ」トレーニングセンタに行かなければならないのを唐突に思い出し、声が漏れた。健康状態を測定するなんとかというスコアが規定値に乗れば、ネクサスの外に出してくれる、というリオとの約束。もともとが不摂生だったためか数値は順調に伸び、約束のラインまでもうひと息。このペースなら、追い込めば今日の午前にでも達成できるかも、というところまできていたのだ。専用ウエアに着替えなきゃ、今着替えたばかりなのに面倒くさい……と思った瞬間、壁面に私の姿が映し出される。窓から鏡に切り替わった壁に360度映るのは、スポーツウエア姿の自分だった。着替えたときにはトレーニングのことは忘れていたはずだったのに、寝ぼけて間違えたのかもしれない。なんだか得した気分になった私は、足取りも軽くセンタへと向かった。
体を動かすことがこんなに気持ちいいなんて。シャワーで濡れた髪を拭きながら、私は小さな達成感に満足していた。鏡に映る肌の張りも髪の艶も、AOに来てから見違えるよう。労働もせず、食事と心地のいい部屋を与えられ、やることといえば適度な運動だけなのだから当然か。日に日に健康そのものになっていく姿を見るにつけ、楽観的な私でもさすがに、一抹の不安がよぎったりもする。まるで、寓話のお菓子の家みたい——そんな懸念も、真新しい服に着替えて、リオを出迎えたときにはどこかへ行ってしまった。ノックなんて無粋なものはなく、彼が部屋に入ってくるのはいつも完璧なタイミングだ。

「ついにスコア到達だね、おめでとう」
開口一番、リオは優しい声音でそう言った。ありがとうリオ、と返す口元が自然に緩むのを自覚する。彼の長身を包む白い衣服は、元いた世界のどんな服とも違う。いくつかの層から成る幾何学的なデザインで、服装から職種を推測することは不可能だった。不思議な意匠を見つめていると、リオの知性に神秘性を付加されるよう。
「もう知ってるんだ。私から伝えたかったのに」
リオが細い指先で自分の左手首を指した先は、バングル型の端末。
「そっか、<ビーイング>ね……」
私も自分の左手首に目を落とす。リオいわく「AO市民の健康を全方位的にサポートし持続的なウェルビーイングを可能にする」腕輪型デバイス。文字情報を伝えるインターフェースはなく、淡く光る乳白色の表面に目を凝らせば、内部に極小の星屑が舞っているのがわかる。「使用者の遺伝子アルゴリズムを可視化したもの」という、星たちが描く複雑な模様は、アメーバのように絶えず分裂・収束を繰り返しながら変形する。
「ビーイングには、あまり驚かないんだね」
「元の世界では私も、似たようなデバイスを使っていたもの」
ビーイングには継ぎ目が見当たらない。輪は伸縮自在で、装着すると使用者に合わせて緩やかに縮み、硬質化する。見慣れてしまったけれど、これだって本来驚くべき技術のはずだ。しかもビーイングはAO全市民に貸与されているという。それが私の腕にも光っているのは悪くない気持ちだ、と親しみを込めてビーイングをなでる。つかの間ここにいることを許された、その証(あか)しのような。
「でも、ほかに驚くことがたくさんあって」
「ケルビムは珍しい?」
私はうなずいて周囲を見回す。壁一面に広がる、外の景色。
「それより、約束したよね。スコア達成したら外に出してくれるって」
「もちろん覚えているよ。今から行こうか、天気もいいしね……」
「やった。ありがとう!」
ケルビムを通してしか見ることのできなかったAO。この未知の街を実際に歩くことができたなら、どんなに素晴らしいだろう。
「ただし僕も一緒に、だけど」
リオがこちらを見つめてほほ笑む。
「それは異存ないけど。でも、メンターって意外と暇なんだね」
20代後半にしか見えないリオが、AOの都市システムをほぼひとりで構築して運営の要を担っていると知ったときは驚いたし、その驚きは街の先進性に触れるにつれ畏敬へと変わっていった。ネクサスで働くオペレータたちはしばしば「Mentor」という肩書きでリオを呼ぶ。役職としては聞き慣れないが、本来こんな軽口を叩ける相手ではないことは容易に推測できる。にもかかわらず、旧来の友人のような接し方をしてしまうのはなぜだろう。
「これも大事な仕事だよ。街をより良くするための」
リオの瞳が真っすぐにこちらを見つめる。知性の奥に強い意志を感じさせる、青緑色の瞳。妙に気恥ずかしくなって、強引に話を変えた。
「それより、そろそろ教えてくれてもいいんじゃない? リオ、あなたはどうして私を呼んだの」
「聞いたことがあるかもしれないけど、時空には特定の場所にゆがみがある。そういうゆがみは時に別の場所……“外の世界”とつながっていることがある。実は量子もつれはそういう道を通じて情報を伝達しているんだ。僕たちはそういった情報を通じて君たちのいた場所とこの場所がつながっていることに気づいた。そういった理論を明らかにすること、その力をほんの一瞬だけ増幅させて、君をここに招くこと。次世代転移機構Universe Metric Distorter……通称<UMD>の試作機はそんなふうに機能している」
リオが左腕を振ると、壁のケルビムに装置の理論らしきものが表示された。私はわざと大きなため息をつく。
「流れからいって、私が聞いてるのは過程じゃなくて理由でしょ。わかってるくせに」
「ごめんね。こういう話ができるのが楽しくて」
本当だろうか。私は確かに、リオと話すのを心待ちにしている。衣食住が満ち足りているとはいえ、私は、この世界ではないどこか——“AOが存在しない世界”、リオの言葉を借りれば“外の世界”から来た異邦人。誰ひとり私のことを知らない世界で、リオだけが私の話し相手になってくれる。ロビンソン・クルーソーだって、無人島で食糧を見つけたときより、フライデーとの出会いのほうがずっとうれしそうだったもの。
それに、私が置かれている状況の特異さを差し引いても、リオとの会話は純粋に楽しかった。彼から聞くAOの話が私にとって未知の世界だから、というのも当然ある。しかし何より、リオの言葉には私を惹きつける何かがあった。おそらく本来は難解であろう都市基幹システムの話も、リオから語られると不思議と頭に染み入っていく。底知れない知性と言葉の節々に表れる誠実さは、凪(な)いだ海に包まれているよう。つたない質問にリオが返答を熟考しているとき、彼の頬にはまつ毛の影が落ちる。私はそれを眺めているのが好きだった。からかっているのか、さっきみたいに煙に巻かれることもあるけれど。
だけれど、それはあくまで私にとっての話だ。リオには、AOに話し相手なんてたくさんいるはず。
私と話していて、むしろ退屈じゃないのかな。
「君を呼んだ理由。申し訳ないけれど、まだ言えないんだ」
「リオが勝手に呼んだのに?」断言するリオに、わざと意地悪く絡んでみる。
「ずいぶん勝手なのね」
有無を言わさず連行された側なのだ、少しぐらい甘えてみてもいいだろう。わざと不機嫌そうにしてみせる私を、リオが真剣な目で見据えた。
「帰りたい?」
「え。……いや、だってリオが、私を呼んだっていうから」
やましいことなど何もないのに、後半は弁解するような口調になってしまった。
AOへようこそ。君のことをずっと待っていたよ——
あの日のリオの言葉をもう一度思い出す。そんな何げない一言を拠(よ)り所に、この世界で安寧を貪る私がおかしいのだろうか。いや、目を背け続けているけれど、本当はわかっている。帰りたくないわけじゃない、リオが帰れと言えば今すぐ帰る。ただ、先延ばしにしていたいだけなのだ。
——いったい何を?
「正確には」
リオの一言に、思考が引き戻された。
「僕が君を呼んだということじゃなくて、この街そのものが君を必要としている……みたいな感じかもしれない」
「ふうん」
リオが、私を呼んだっていうから。八つ当たりみたいに放った一言を、彼は真剣に考えていてくれたらしい。そう思うと申し訳なくなった。
「街が、必要としている? 私を?」
それにしても、どういうことだろう。AOが私を求めている、とはなんのたとえなのだろうか。口に出してつぶやいてみたが、リオはケルビム越しの景色を見つめたまま何も言わない。まあいいか。リオがそれ以上説明しないということは、今はまだわからなくても構わないのだろう。そんなことより、今日は念願の外出日だ。私の考えを読んだかのように、リオがこちらを振り向いた。
「もちろん、大事なことはいずれ話すから心配しないで。まずはAOを見てもらってからかな……」